本文
大分県の特産品(スギ)
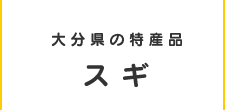

1.いつから生産され始めたの?
「盛んに植えられ始めたのは、江戸時代からなんだよ。」
県内のスギは、ほとんどすべてが人の手によって植えられたものです。特に日田地方では江戸時代から盛んに植えられており、日本有数の産地になっています。

日田市のスギ材
2.生産量や生産額などはどのくらい?
「生産量は65万立方メートルで、全国第4位なんだよ。(2010年)」
県内にはスギが6千3百万立方メートルあって、全国第3位です((2007年度)の民有林(国が管理している山ではない山))。この豊富な資源をもとに、すべての市町村でスギが生産されています。
また、出荷された製材品の量は44万立方メートルで、全国6位です(2010年)スギ以外もふくむ)。
3.どこで生産されているの?
「西部の日田市と南部の佐伯市が多いんだよ。」
県内すべての市町村で生産されていますが、江戸時代から植林されている日田地域と、約50年前から盛んに植林された佐伯地域で、特に多く生産されています。
4.どうやって生産するの?
「生産するまでにはさまざまな作業が必要で、人の手で大事に育てられています。」
作業1 植え付け スギを育てるには、まず苗木を山に植えることから始めます。植える本数は、1ヘクタール当たり2,000~3,000本くらいです。
作業2 下刈り 植えた後、自然に生えてくる他の草や木に負けないよう、草刈りをすることを「下刈り」といいます。下刈りは、他の草や木が大きくなる夏にするので、暑くて大変です。

作業3 枝打ち 木の成長にあわせて枝を切り落とすことを「枝打ち」といいます。枝打ちをすると、将来スギをきって加工したときに、節(ふし)が少ない柱や板になるため、高い値段で売ることができます。

作業4 間伐(かんばつ) 木の成長を良くするために、ある割合で木を間引くことを「間伐」といいます。スギが大きくなってくると、となりのスギと太陽の光の取り合いをすることになり、成長が悪くなります。このため、スギの成長にあわせて何回か間伐をする必要があります。また、間伐をせずそのままにしておくと、林の中がだんだん暗くなり、草が枯れて、表面の土が流れ出します。山を健康な状態に保つためにも、間伐を行うことはとても重要です。
※木を切るときは、「伐る(きる)」という漢字を使います。

間伐が遅れているスギ林
間伐が行われているスギ林
作業5 主伐(しゅばつ) 40~50年育てて、十分に大きくなった木を伐ることを「主伐」と言います。木を伐るために、昔はオノやノコギリを使っていましたが、今では「チェーンソー」という機械で伐るため、作業が楽になりました。また最近では、「ハーベスタ」などのチェーンソーがついた大きな機械が開発されており、人が機械に乗ったままスギを伐ることができるようになりました。

チェーンソーによる伐採
ハーベスタによる伐採
5.どうやって利用されているの?
「家の柱や家具のほか、紙などに利用されています。」
伐られたスギは、製材(せいざい)工場でさまざまな形に加工された後、大工さんに届けられて家の材料としたり、机やイスなどの家具の材料などとして利用されています。また、製材するときにでる木の粉は牛の寝床などに、切れはしは紙の原料などに利用されています。
6.家のどんなところに利用されているの?
「割れが少なく色も香りも自然に近い、大工さんに評判の『大分方式乾燥材』!」
木造住宅では、柱や壁、土台、屋根など、あらゆる場所で利用されています。木造ではない住宅やコンクリートのビルでも、床や壁などに板として利用されています。
また、家の材料としてスギを利用するには、よく乾かすことが必要です。じゅうぶんに乾かした木材を「乾燥材(かんそうざい)」といいます。これまでは、鉄の箱の中に木材を入れ、温度をとても高くして1週間くらい入れたままにすることで乾かしていました。でも、この方法では木材の表面や中身が割れたり、色が焼けたように黒っぽくなったり、香りが悪くなるという問題がおきていました。そこで、県と製材所が協力して研究し、木材の割れが少なく、色や香りが自然に近いままで、じゅうぶんに乾かす方法を開発しました。この方法で乾かした木材を「大分方式乾燥材」と呼んでおり、その品質は全国的にとても高く評価されています。

木造住宅の骨組み
大分方式乾燥材
こんなこともあるよ
「森林は、雨水をため、こう水を防ぐなど、私たちのくらしを守ってくれているんだ。」
森林は、大雨がふっても水をためて、少しずつ川に流すので、こう水を防いでくれます。ほかにも、土砂くずれを防いだり、動物のすみかになるなど、さまざまな役割をしてくれています。
また、植物は二酸化炭素を吸って、私たちが呼吸するのに必要な酸素を出してくれていますが、木は炭素をためておくことができるので、地球の温暖化を防ぐことについて、とても大事な役割をはたしています。
くわしく知りたい人は、下のホームページを見てください。
林野庁ホームページ「こども森林館」 http://www.rinya.maff.go.jp/kids/





