本文
大分県の特産品(ホオズキ)
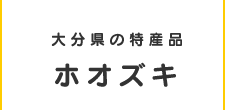

1.いつから生産され始めたの?
「大分県でホオズキの生産が始まったのは1988年頃なんだよ。」
ホオズキはナス科の多年草で、ヨーロッパ~アジアの温帯が原産地で、古くから薬用と観賞のために栽培されてきました。
日本では、江戸時代に7月の初めに色付く園芸品が流行し、これに併せた「ほおずき市」が各地で開催されています。特に東京浅草の浅草寺で7月9,10日に開催される「ほおずき市」は有名です。
県内では、1988年頃に宇目町(現在の佐伯市宇目)でホオズキ栽培が始まり、現在では県内各地で栽培されています。
2.生産量や生産額などはどのくらい?
「大分県のホオズキ生産量は全国第1位!」
大分県は、生産額で全国1位のホオズキ産地であり、全国の生産額の4割以上を占めています。
大分県のホオズキは、生産者に丹念に育てられ、実が大きくて実付きも良く、市場等から高い評価を受けています。

3.どこで生産されているの?
「県内では南部の佐伯市や杵築市で栽培されています。」
全国では、静岡県や宮崎県、熊本県で生産されています。
県内では、佐伯市の他に杵築市や豊後大野市等、県内各地で栽培されています。
4.どうやって生産されているの?
「実が赤く熟した頃、7月の新盆と8月の旧盆に出荷します。」
ホオズキは、収穫後の株を使って、地下茎を増やします。12~2月に親株を堀上げて、地下茎を約12cm(2~3節)の長さに切って、それを1~3月に定植します。
5月下旬に30cmぐらいの大きさになるので、1株ごとに支柱を立てます。
実が赤く熟れた7月の新盆と8月の旧盆に出荷します。

5.どのように使われるの?
「お仏壇の仏花として使われています。」
ホオズキはお盆の時期に、先祖の霊を迎えるための精霊棚(盆棚)や仏花として飾られます。




