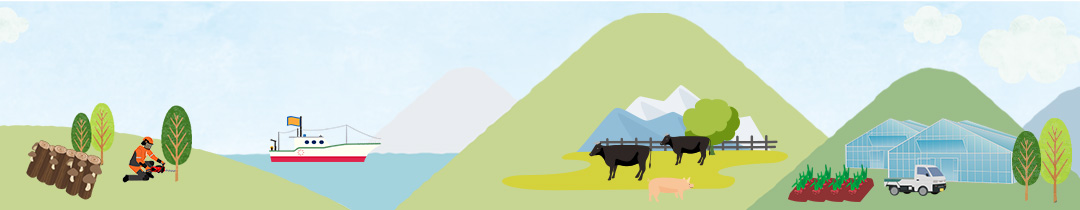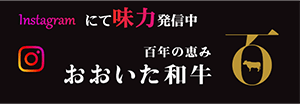本文
「農林水産研究タイムリー情報」試験研究の現場から旬な情報をお届けします!

現在届いている情報は以下のとおりです。マスコミ各社の皆さんが興味を持たれましたら、各研究部、グループが積極的に対応いたしますので、ご連絡ください。
(過去のバックナンバーはページ下段のPDFファイルでご覧いただけます。)
2月14日(1)農薬指導士新規認定研修会で講演しました
農業研究部:2011 発信:2026年2月14日 掲載期限:2月28日
2月5日に大分市で農業団体職員や農業関係企業関係者など156名が出席して開催され、病害虫対策チームから、病害虫の生態および防除の考え方について講演を行いました。今後も研究会や研修会などを通して病害虫防除の情報共有や防除技術の向上に取り組んでいきます。

●問合せ先
農業研究部 病害虫対策チーム
0974-28-2078
2月10日(2)県樹苗協との共同試験発表会
林業研究部:2010 発信:2026年2月10日 掲載期限:2月28日
当研究部では、県樹苗協と共同で苗木生産に関する試験を実施しており、1月29日に林業研究部会議室において発表会を開催しました。生産者等24名を対象に、研究成果の発表を行いました。
今回の発表成果を踏まえ、今後の取り組みに対する展開の要望や生産現場における課題などの情報交換を行いました。
この共同研究は引き続き継続し、生産現場の問題の把握と成果の早期普及に努めます。


●問合せ先
林業研究部 企画指導担当
0973-23-2146
2月10日(1)林業研究部研究発表会
林業研究部:2009 発信:2026年2月10日 掲載期限:2月28日
1月27日に当研究部会議室において令和7年度の林業研究部研究発表会を開催し、56名の参加をいただきました。完了予定課題を含む4課題の研究成果について発表を行い、参加者から様々なご質問をいただきました。
今回の発表内容については、追加試験の内容を加えて、年報等で発表していきます。


●問合せ先
林業研究部 企画指導担当
0973-23-2146
2月8日(1)白ねぎの有機質肥料活用試験を実施しました
農業研究部:2008 発信:2026年2月8日 掲載期限:2月28日
化学肥料の価格が高騰していることから、肥料コスト削減を目的とした試験を実施しています。低コストな有機質肥料「鶏糞ペレット」や「混合堆肥複合肥料」を施用しても、化学肥料と同等の収量を得ることができました。生産者に評価される研究成果となるよう、来年度も引き続き試験を実施します。

●問合せ先
農業研究部 葉根菜類・茶業チーム
0974-28-2082
2月7日(1)水田農業グループで研究員の資質向上のためゼミを行いました
水田農業グループ:2007 発信:2026年2月7日 掲載期限:2月28日
1月13日、水田農業グループが定期的に行っているゼミを開催しました。今回は北部振興局の黒木専門員を講師に、宇佐市でのエダマメ産地の成功事例についてお話しいただきました。このゼミでは、全く新しい産地をどのようにして作り上げるのか、関係機関や試験場との連携などの取り組みについて学びました。また津守研究員からは雑草の研修会の報告を行い、雑草の調査方法について学びました。今後も現場に寄り添った試験設計を行い、現場で役立つ農業技術の開発に取り組んでまいります。


●問合せ先
水田農業グループ 企画指導担当または水田農業チーム
0978-37-1160
2月6日(1藻類増養殖に関する専門家から助言をいただきました
北部水産グループ:2006 発信:2026年2月6日 掲載期限:2月28日
当グループではヒジキ養殖をはじめとした海藻類の増養殖に関する技術開発に取り組んでいます。このたび水産大学校で藻類増殖学がご専門の教授をお招きし、取り組みについて助言をいただきました。今後の研究活動に活かしてまいります。

●問合せ先
北部水産グループ 養殖環境チーム
0978-22-2405
2月5日(1)イチゴ栽培技術勉強会でうどんこ病対策を指導しました
農業研究部:2005 発信:2026年2月5日 掲載期限:2月28日
農業研究部では、2月2日にイチゴのうどんこ病に対する注意報を発表しました。本病への対策強化のため、1月26日に広域普及指導員主催の「いちご栽培技術勉強会」が開催され、普及指導員を中心に17名が参加しました。当チームから、本年度の発生要 因、新規薬剤を含む殺菌剤の特性や効果的な使用方法について指導しました。出席者からは気門封鎖剤や展着剤の混用の是非や散布間隔の考え方等について質問がありました。今回の内容は、普及指導員等を通じて生産者に情報共有します。

●問合せ先
農業研究部 病害虫対策チーム
0974-28-2078
2月4日(1)革新的稲作技術の研究推進会議が大分県で開催されました
水田農業グループ:2004 発信:2026年2月4日 掲載期限:2月28日
1月28日、29日生研支援センター「オープンイノベーション研究・実用化推進事業」の支援を受けて行っている「初冬から早春まで「いつでも直播」:春の作業ピークを平準化できる革新的稲作技術」の研究推進会議が大分県で開催されました。この研究は、冬から早春の間にイネの種もみを直播することで、春先の農作業を分散することができ、大規模農家の負担軽減などにつながることが期待されます。本年度の研究結果、残された課題について検討を行い、2日間にわたり活発な情報交換、議論をしました。


●問合せ先
水田農業グループ 企画指導担当または水田農業チーム
0978-37-1160
2月3日(2)令和7年度園芸品評会の審査会に研究員が出席
果樹グループ:2003 発信:2026年2月3日 掲載期限:2月28日
毎年開催される杵築市農林水産祭の農産物品評会では、当グループの研究員が事前審査に立ち合います。1月16日に杵築市で開催された審査会では、管内の生産者からハウス中晩柑、露地中晩柑、温州ミカンで総数81点の応募がありました。全体のレベルが高い中、果実の食味や外観に関する厳正な審査が行われ、最優秀賞が6点、優秀賞11点が選ばれました。

●問合せ先
果樹グループ 温州ミカンチーム
0978-72-0408
2月3日(1)運搬車を活用した低コストな防除技術の試験を開始
果樹グループ:2002 発信:2026年2月3日 掲載期限:2月28日
近年、果樹の大規模経営で一般的なスピードスプレイヤ(高額な病害虫防除機械)は価格が値上がりし、導入へのハードルが高まっています。よって当グループでは、R7年度から低コストで汎用性の高い運搬車を用いた病害虫防除技術の確立を目的とし、樹形改造や薬剤散布方法の最適化といった試験研究に取り組んでいます。

●問合せ先
果樹グループ 温州ミカンチーム
0978-72-0408
1月28日(1)イチゴの新品種を研究しています
農業研究部:2001 発信:2026年1月28日 掲載期限:2月28日
大分県のオリジナル品種の育成に取り組んでいます。令和3年には「大分6号(ベリーツ)」が品種登録されましたが、農業研究部では毎年2、000個以上の種子をまいて、生育が良好で色や味の優れたものを選抜しています。旬を迎えたこの時期には食味試験を行い、有望系統を評価しました。

●問合せ先
農業研究部 企画指導担当
0974-22-0671
1月24日(1)きのこグループ研究発表会を開催
きのこグループ:2000 発信:2026年1月24日 掲載期限:2月28日
1月20日に令和7年度きのこグループ研究発表会を開催し、生産者など約70名の参加がありました。
研究発表課題は以下のとおりです。
(1)原木の伐採・玉切り時期の検討 (松本研究員)
(2)乾シイタケの機能性成分について(豊田研究員)
(3)新品種9-46(仮称)の特性評価試験(石原主幹研究員、寄井田広域普及員)

●問合せ先
きのこグループ きのこチーム
0974-22-4236
1月20日(2)イチゴのウイルスフリー苗を出荷しました
農業研究部:1999 発信:2026年1月20日 掲載期限:2月28日
農業研究部で生産した県オリジナルイチゴ「ベリーツ(大分6号)」のウイルスフリー苗(原種)400株を許諾先である全農おおいたに出荷しました。
今後は2次増殖を行う民間事業者により、苗数を25倍程度に増やし、R9年度の栽培に向けて県内各地の生産者へ販売されます。


●問合せ先
農業研究部 果菜類チーム
0974-28-2081
1月20日(1)小型堆肥化装置を使用した堆肥化試験を開始しました
農業研究部:1998 発信:2026年1月20日 掲載期限:2月28日
化学肥料の使用量を減らすためには、有機質資材(堆肥)の積極的な活用が必要です。その際、問題となるのが堆肥の臭気です。堆肥の製造過程において、強い臭気が発生する要 因を解明するため、小型堆肥化装置を用いた試験を開始しました。これまでの処理方法を改善して、臭気の少ない堆肥製造を実証します。

●問合せ先
農業研究部 土壌・環境チーム
0974-28-2072
1月19日(1)カンキツ貯蔵病害の対策について
果樹グループ:1997 発信:2026年1月19日 掲載期限:2月28日
貯蔵中のカンキツを腐敗させる主因として、貯蔵病害(緑かび病、青かび病、軸腐病)があります。現在、貯蔵病害に対して広く使用されていた農薬の登録失効に伴い、代替剤の効果検証が進められ、当チームでも薬剤試験を行っています。貯蔵病害を防ぐには、収穫前薬剤散布とともに、収穫時に果実を傷つけないように丁寧に扱うことが重要です。

●問合せ先
果樹グループ 温州ミカンチーム
0972-72-0407
1月18日(1)基盤整備圃場における局所排水不良対策の指導
農業研究部:1996 発信:2026年1月18日 掲載期限:2月28日
竹田市高源寺地区において、豊肥振興局など関係者と夏秋ピーマン生育不良箇所の排水改善対策を実施しました。
現地は下層土が強粘土質のため、地下にある暗渠排水管まで水の浸透が不十分でした。その改善のため、サブソイラによる心土破砕と同時に多孔性資材である「クリンカアッシュ」を投入しました。
次年度の栽培で効果が実感できるよう指導します。
※クリンカアッシュとは、火力発電所で石炭を燃焼させた時に発生する石炭灰のことです。
※暗渠排水管(あんきょはいすいかん)とは、地中に埋め込まれた水路のことです。
※サブソイラとは、下層の硬い土に亀裂を入れて破砕する農業機械のことです。

●問合せ先
農業研究部 土壌・環境チーム
0974-28-2072
1月17日(1)日田高校「日田杉」勉強会
林業研究部:1995 発信:2026年1月17日 掲載期限:2月28日
12月18日、県立日田高等学校2年生5名が「日田杉の性質を調べ、日田杉を広めたい」との意識のもと「建築材料としての日田杉の強度」について自主探求授業の一環で、当研究部を訪れ、勉強会を開催しました。
勉強会では、品種、材質、強度等の特性についての考え方を学び、実際に実大強度試験を見学しました。自分達で考えてきたことに加え、現場の知識を得ることで今後の取り組みがさらに深まることを期待しています。


●問合せ先
林業研究部 企画指導担当
0973-23-2146
1月16日(1)水田農業グループ試験研究アドバイザー会議(完了課題結果検討会)を開催しました
水田農業グループ:1994 発信:2026年1月16日 掲載期限:1月31日
12月18日、九州大学の助教と農研機構のグループ長をアドバイザーとしてお招きし、水田農業グループのR8年新規課題と完了課題について検討を行いました。大豆新品種の栽培試験と水稲高温対策における新規試験については、的確なアドバイスをいただきました。完了課題については、評価をいただくとともに、今後の普及方法についてのご意見をいただきました。また、若手研究員とも積極的に意見交換し、有意義な会議となりました。今後も試験研究の精度向上のため、このような会議を開催する予定です。

●問合せ先
水田農業グループ 企画指導担当または水田農業チーム
0978-37-1160
12月29日(2)潜水訓練
水産研究部:1993 発信:2025年12月29日 掲載期限:1月31日
当研究部では、藻場や放流魚介類の研究の一環として、潜水調査を行っています。潜水調査は、慣れないうちは思うようにいかないこともあるため、事前の準備や訓練が大切です。
そのため、12月17日に潜水調査を行う研究員を対象に、潜水の基礎訓練を実施しました。特に今年度初めて潜水調査に取り組む研究員にとって、大変有意義な訓練となりました。

●問合せ先
水産研究部 企画指導担当
0972-32-2155
12月29日(1)10月採卵ブリ種苗 現地養殖試験開始
水産研究部:1992 発信:2025年12月29日 掲載期限:1月31日
当研究部では、春の産卵期における養殖ブリの成長と品質低下の対策として、産卵を秋(10月)に行う技術開発を行っています(タイムリー情報No1945 (2025年10月28日 発信))。12月17日、順調に成長した全長8cmのブリ種苗約1万尾を蒲江の養殖場へ出荷しました。今後、出荷したブリの成長・品質を養殖業者とともに調査していきます。

●問合せ先
水産研究部 企画指導担当
0972-32-2155
12月28日(1)海でのアユの生態を探る第一歩
北部水産グループ:1991 発信:2025年12月28日 掲載期限:1月31日
川でふ化して海に流下したアユが、翌年の春に川を遡上するまでの間、海でどのように生活しているかはあまりよくわかっていません。まず広い海で小さなアユを捕まえることが困難です。このため大分川河口付近でトラップによる捕獲を試みました。光に集まる習性を利用したトラップを使用したところ、小さなアユを捕獲することができました。


●問合せ先
北部水産グループ 養殖環境チーム
0978-22-2405
12月27日(2)2026年度果樹病害虫防除暦の検討会議を行いました
果樹グループ:1990 発信:2025年12月27日 掲載期限:1月31日
今年は高温の時期が長く続いたことや降水量が少ない影響で害虫の発生状況も例年と異なり、防除が難しい年でした。特にサビダニの被害が多く見られ、秋の防除の重要性を認識させられました。
今後、防除の効果やコスト、防除のしやすさなどを踏まえて、より良い薬剤への入れ替えを検討し、生産者にとってわかりやすく役に立つ暦の作成に取り組んでいきます。

●問合せ先
果樹グループ カボス・中晩柑チーム
0978-82-2837
12月27日(1)R7園芸学会(秋)でハウスミカン光合成とCO2局所施用について発表
果樹グループ:1989 発信:2025年12月27日 掲載期限:1月31日
当チームでは、国や大学等と共同でハウスミカンの収量向上に向けた研究に取り組んでいます。一部成果が得られたので、高知大学で開催された園芸学会において、新たな光合成評価法とハウス内CO2濃度分布に関する研究について発表を行いました。本発表では、好意的な意見や研究方法に関する専門家からの助言などが得られ、今後の業務への参考となりました。
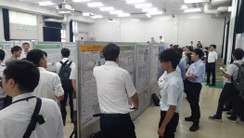
●問合せ先
果樹グループ 温州ミカンチーム
0978-72-0407
12月26日(2)「水田輪作新技術プロジェクト」キックオフフォーラムに参加しました
水田農業グループ:1988 発信:2025年12月26日 掲載期限:1月31日
12月11日に国の研究機関である農研機構主催の標記フォーラムが開催され、研究員が参加しました。水田農業では農業従事者の減少と担い手の大規模化が進む中、新技術の導入による生産性向上が急務となっています。本県でも同様の課題に直面しており、最新の情報を収集し必要に応じて国と連携も実施し、課題解決のための試験研究に取り組んでいます。

●問合せ先
水田農業グループ 企画指導担当または水田農業チーム
0978-37-1160
12月26日(1)農業のリスク管理講習会に参加しました
水田農業グループ:1987 発信:2025年12月26日 掲載期限:1月31日
12月11日に農業者や関係機関を対象とする標記研修会が開催され、試験場の研究補佐をする職員が参加しました。農作業上の危険なポイントを学び、「G A P」を上手に活用してリスク管理を行うことの重要性を学びました。今後は、工程管理を意識して農作業事故の防止に努めるとともに、一層の生産安定、品質向上を目指します。

●問合せ先
水田農業グループ 企画指導担当または水田農業チーム
0978-37-1160
12月25日(1)施肥防除対策研修会で発表しました
農業研究部:1986 発信:2025年12月25日 掲載期限:1月31日
12月10日に県および肥料植物防疫協会主催の施肥防除対策研修会が開催され、JA職員、農薬メーカー及び普及指導員を含め141名が参加しました。当チームの研究員から「防除指導指針の改訂」、「今年度の病害虫発生状況」、「トマトキバガの生態と防除」について説明および発表を行いました。引き続き、病害虫防除の情報共有や防除基準策定、まん延防止に取り組んでいきます。

●問合せ先
農業研究部 病害虫対策チーム
0974-28-2078
12月24日(2)転炉スラグを利用したニンジンの栽培試験
農業研究部:1985 発信:2025年12月24日 掲載期限:1月31日
転炉スラグは、製鉄所の製鋼工程で生成される副産物で、土壌p Hを長期的に安定して維持できる優れた土壌改良資材です。本試験では、転炉スラグを散布した畑でニンジンを栽培し、収量性等を調べています。今回は抜き取り調査を実施し、収穫したニンジンの収量および品質の調査、ならびに植物体中の養分含有量について分析をしました。引き続き、転炉スラグがニンジンの生育や養分吸収に与える効果を明らかにしていきます。

●問合せ先
農業研究部 土壌・環境チーム
0974-28-2072
12月24日(1)大規模園芸団地予定地の土壌調査を実施しました
農業研究部:1984 発信:2025年12月24日 掲載期限:1月31日
企業参入による飯田高原での葉ねぎの生産拡大に向け、九重町の圃場約10haにおいて、西部振興局と合同で簡易な土壌断面調査を行いました。今回は、深さ40cm程度の穴や、検土杖(けんどじょう)を用いた調査により、土壌の種類や礫の存在について確認しました。
今回の結果に基づいて、圃場整備事業等により葉ねぎに適した土壌への改良を検討します。
※検土杖とは、大きな穴を掘らずに、土壌の深さや土質を垂直に採取・調査するための道具で、ボーリングステッキとも呼ばれます。(写真)

●問合せ先
農業研究部 土壌・環境チーム
0974-28-2072
12月19日(1)ヒジキ養殖ロープの作成が最盛期です
北部水産グループ:1983 発信:2025年12月19日 掲載期限:1月31日
当グループが開発したヒジキ養殖手法では、種苗をロープに挟み込み、それを海に出して養殖を行います。人工種苗をはじめとしたさまざまな種苗で養殖ロープを作成して研究を進めており、この時期は養殖ロープの作成に大忙しです。


●問合せ先
北部水産グループ 養殖環境チーム
0978-22-2405
12月17日(1)ヒジキ試験養殖漁場を設定しました
北部水産グループ:1982 発信:2025年12月17日 掲載期限:1月31日
当グループでは人工種苗を使ったヒジキ養殖技術開発に取り組んでいます。人工種苗を実際に使って養殖を行うための漁場を宇佐市沖の干潟上にノリ養殖漁業者の協力も得て設定しました。
この時期は大潮でも夜間から早朝にかけて大きく潮が引くため、早朝の暗いうちから干潟上に養殖ロープを張るための支柱を建てました。


●問合せ先
北部水産グループ 養殖環境チーム
0978-22-2405
【R7バックナンバー移行済み情報】 令和8年1月22日時点・152件