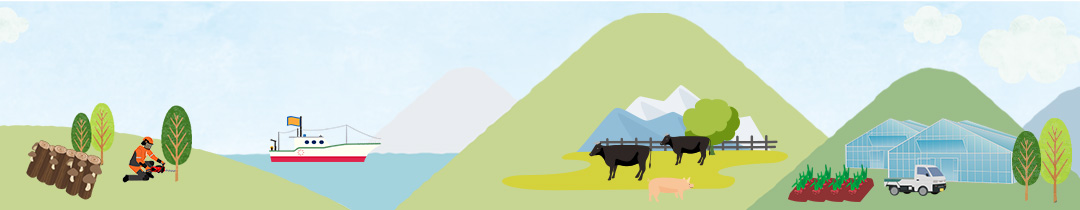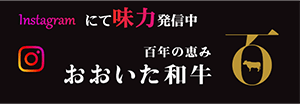本文
国東市 カボス団地

|
〇経営体情報 |
|
〇参入スケジュール |
|
〇活用した支援事業 |
団地との出会いから就農を決意
大規模園芸団地との出会いから、これまで経験のなかった農業に挑戦することになり、新規原料の生産という新規事業に着手することになったという(株)ハマノ果香園。濱野光展社長に、営農開始までの経緯から今後の展望までをお伺いしました。

【参入のきっかけ】
造成&定植中の団地を紹介され、挑戦するハードルが下がった
―― 御社の拠点は広島県ですが、大分県との接点はいつ頃からあったのでしょうか?
当社では、瀬戸内の柑橘類をメインに果汁や加工原料等として製造・販売を行っています。大分県との接点は2005年頃から、カボス果汁を販売するようになったのがきっかけでした。自社製ストレート果汁のラインナップを増やそうと商品開発を進める中で、カボスに着目し、国内随一の産地である大分県の市場で果実を仕入れるようになったんです。販売してみると好評で、順調に需要も伸びていきました。
―― 大規模園芸団地に参入することになった理由は?
昔から当社では、原料となる柑橘を主に生産者さんから直接仕入れてきました。ですので、長い会社の歴史の中で農業に取り組んだ経験はありませんでしたし、「やってみよう」と考えたことさえなかったのですが、ある時、カボスを仕入れていた市場の担当者の方から「大分県が整備している大規模な農園があり、企業が参入できる」と教えていただきました。また、その方は大分県のほうにも「カボスを購入している企業がある」と私たちのことを紹介し、縁を繋いでくださったんです。そして、国東市にある広大な温州みかんの遊休農地を紹介していただきました。
―― 農業参入に、どんなメリットを感じたのでしょうか?
生産から取り組むこと自体が自社の強みになりますし、価格決定にも有利だと考えました。柑橘の収穫は年に1回。果汁の販売価格は収穫の数か月前に取引先と交渉するのですが、その年にどれだけ販売できるのかについては、収穫量などが読めていなければ適切な数字が提示できません。従来は生産者さんに話を聞きながら決定していたのですが、自分たちで生産を手掛ければ、いち早く正確なデータが出せるところもメリットだと感じました。

―― とはいえ、初めての農業。挑戦を決意できた理由は?
有り難かったのは、紹介いただいた農園が、すでに大分県の事業でカボス団地として造成・定植が進められているものだったこと。県外からの参入ですので、造成するにも地元の業者さんを知りませんし、そもそも知識がない状態でしたから、すぐに営農を始められる環境だということで、挑戦するハードルが下がりました。そこで、2007年に(株)ハマノ果香園を設立して参入の準備にとりかかり、造成とカボスの苗木の定植が終わった団地を大分県農業農村振興公社から購入。2009年に営農を開始しました。
【経営状況】
高まるカボスの需要。常時雇用のために野菜も栽培
―― 営農開始当時の状況は?
参入当時は、カボスの樹が1万7000本、面積は22haという日本最大規模のカボス団地としてスタートしました。樹が植っていても、収穫できるようになるまで3年ほどかかります。その間、大分県の方が何度も営農指導に来てくださり、栽培方法を教えてくれたことも有り難かったです。また、県の方は、活用できる行政の事業があれば知らせてくれたり、その資料作成も手伝ってくれたりと、手厚くサポートしてくださいました。おかげでカボスは2012年から収穫できるようになり、その3年後の2015年くらいから本格的な収穫量が確保できるようになりました。
―― 雇用はどのように行いましたか?
新たに地元の方を従業員として雇用しました。加えて繁忙期には広島で雇用している外国人技能実習生を国東に派遣し、活躍してもらっています。できれば繁忙期にも地元の方を雇用したいのですが、カボスの収穫時期は米をはじめ農作物の収穫が重なる時期ですから、なかなか人材募集に苦労しています。また、カボスの栽培には手のかからない時期もあります。そこで、従業員を常時雇用するため、別の土地に野菜用の圃場を借りて、トマトやスナップエンドウなどの栽培にも取り組んでいます。野菜部門には、地元の生産者の方を管理者として雇用しました。現在はカボスと野菜、それぞれに責任者を置いて管理をしています。

―― 経営状況はいかがですか?
カボスは、まろやかな風味と香りのバランスが良いことから年々、需要が伸びています。ポン酢やお酒の原料にカボスを使いたいというメーカーさんが増えているからだと思います。それに比例して私たちの栽培技術も向上してきて、2023年は過去最高の収穫量(470t)を記録しました。ただし、人手のかかる野菜の栽培により大きなコストがかかるので、カボスでもう少し利益を出し、バランスの良い経営を目指していきたいと考えています。
【大規模園芸団地のメリット】
団地内に搾汁工場を併設し、品質の向上を実現

―― 大規模園芸団地に「参入して良かった」と思う点は?
何より、果汁の品質を向上できたことです。市場で調達していた頃は、それを広島に持ち帰って搾汁していましたが、営農開始後ある程度の収穫量を確保できるようになり、団地内に搾汁工場を建設することにしました。工場は2019年春に完成し、ここで搾りたての果汁を鮮度を保ったまま冷凍保存することが可能になりました。団地面積が広大なので、新たに土地を探すことなく敷地内に工場を建てることができ、品質の向上が実現しただけではなく、果実をそのまま運ぶ時より輸送コストも削減できました。
また、広大カボスな団地には車が通れる道が確保されているため、大型の農業機械を導入できたのもメリットです。カボスに関しては、果実を運ぶトラックや、下草の除草、病害虫防除のためのスピードスプレーヤを活用しています。

【今後の展望】
担い手不足の中、大規模に生産を続ける価値を実感
―― 今後の課題は何ですか?
カボスには表作・裏作があり、隔年で収穫量にバラツキが出ます。例えば、2024年の収穫量は前年の半分程度にとどまり、需要に応えるため社外からの仕入れにも奔走しなければなりませんでした。表裏があることは前提として、やはりバラツキは抑えたいところ。そこで、今後はできるだけ樹の成長に気を配り、管理に人の手をかけて、できるだけ収穫量に大きな差が出ないよう努力していきたいです。それから、団地が斜面にあることから、6段ある果樹園の上下で樹の生育が違うのも課題。雨水によって養分が流れやすい上のほうの樹が大きくなるように、またよく育った下のほうの樹は今後も十分に果実がなるように、育てていきたいと思います。


―― 大規模園芸団地への参入を検討している方々に、アドバイスをいただけますか?
当社にはもともと販路があったので、目標とする収穫量とそれに必要な経営面積が産出できましたが、“つくる”ことが先だと、計画を立てるのに苦労するのかもしれません。あらかじめ販路の目処をつけておくことをおすすめします。また、大分県外から参入する場合、遠隔地からの管理になると従業員にも作物にも目が行き届きませんし、近年は異常気象の影響で作業のマニュアル化も難しいと感じています。自社に合ったやり方で、どういう雇用スタイルを採用するのかも鍵になると思います。
―― 最後に、これからの目標を教えてください。
全国のカボスの生産量の99%は大分県で産出しています。担い手不足の現状がある中、需要は年々高まっており、だからこそ参入した団地のような規模で生産を続ける価値を感じています。2022年には、カルビー(株)から発売された「ポテトチップス九州味自慢 九州産かぼすと塩味」に当社のカボス果汁を使っていただいたのですが、その後も大手企業さんから商品開発のご相談を受けています。こうした期待に応え、どんどんカボスの良さを広げていけたらいいですね。