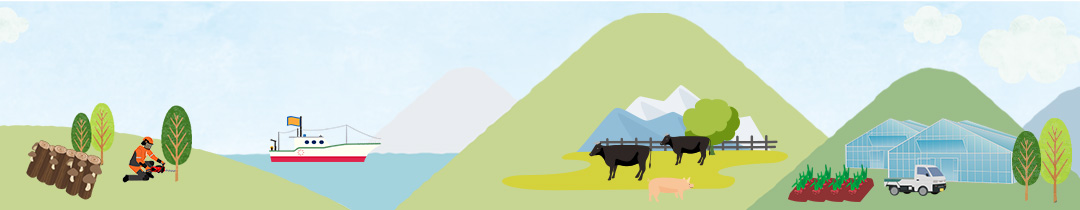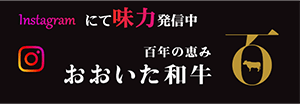本文
竹田市 スイートコーン・キャベツ団地

|
〇経営体情報 |
|
〇参入スケジュール |
| 〇活用した支援事業 ・県営畑地帯総合整備事業 |
農地集約で作業効率UP!
生産者の高齢化にともなって耕作放棄地が増えている昨今、その活用を任される経営体が増えている現状もあります。その場合、点在する圃場間の移動に時間を要するなど、生産性が悪くなるのが課題となっていますが、竹田市の河野公明さんは、県の事業を活用して農地を大規模に集約し、作業の効率化を叶えました。

【参入のきっかけ】
「点在する小さな圃場を集約するチャンス」だと思った
―― 竹田市菅生の生産者さんたちは、どんな作物を栽培していますか?
標高500m前後の地域にあり、夏でも比較的涼しい高冷地の気候を活かして、スイートコーン、キャベツ、ニンジン、レタスなどを育てている生産者が多いです。私は20歳の時に家業を継いで以来、40年以上にわたって主にスイートコーンとキャベツの生産をしてきました。高冷地といっても、地球温暖化の影響で近年は真夏が高温になり、タネを播いた後、芽が出るべき時期に出ないなど、天候を見極めながらの作付となっています。従来の雨水頼みでは十分な収穫量を得ることも難しくなってきました。そんな中でも結果を出せるよう、畑かん用水を活用するなど最善の努力を続けています。

―― 大規模園芸団地に参入することになった理由は?
2019年から、菅生地区では国道57号の北側に位置する平井と今にまたがる34haの土地において県営畑地帯総合整備事業(竹田西部3期地区)が進められています。もともと、ここには畑地と牧草地が混在しており、そのうち大分県酪農振興公社が約7割、個人の生産者が約3割の土地を所有していました。私の圃場も、その一部だったんです。今回の事業は、いったんそれぞれが持っていた小さな土地を集約して大きな区画形状に整え、生産性の高い大規模圃場を造り替えるもの。所有者たちには改めて区画が割り振られることになり、これまで別の場所にも転々と所有していた圃場を集約するチャンスだと考えました。
―― 不安はありませんでしたか?
作付を行わない時期に工事が進む予定になっていたので、生産スケジュールに影響はありませんでしたし、40年ほど前に行った基盤整備の経験から、どんなリスクがあるかも想定できていましたので、不安はありませんでした。
【経営状況】
新しい圃場で、売上が約1.5倍に向上!

―― 営農開始当時の状況は?
2022年に、新しい区画で栽培を始めました。34haの団地のうち、私が経営する面積は3.4haあり、圃場は集約されているので広大です。40年前の基盤整備の時、造成する際に重機で大地を踏み固めるせいか、新しい圃場で排水が悪くなった経験があります。それを踏まえて、今回は新しい圃場でも上手く対処ができたと思います。通常、作付は春秋の年2回行いますが、団地内では秋の作付をせず、代わりに緑肥を植えてまずは土づくりに専念したんです。その間は、知り合いが耕作放棄地にしている圃場を団地外に借りて作付したり、最近はトラクターアタッチメントで排水対策をすることもできます。なるべく安定的に作物をつくる努力を惜しみませんでした。
―― 経営状況はいかがですか?
野菜の高値が続いている影響もありますが、2024年の売上は前年の約1.5倍程度に膨らみました。しっかり土壌づくりができた成果と、やはり大規模園芸団地の中に圃場を集約できたことのメリットが大きいと思います。
【大規模園芸団地のメリット】
大型トラクターの導入でいちどに作業可能に
―― 大規模園芸団地に「参入して良かった」と思う点は?
圃場が集約できたことで、作業効率がとても良くなりました。どの地域でもそうだと思いますが、近年は高齢化によって耕作放棄地が増え、私も生産を止めた知り合いから託された畑がいくつかありました。それも含めて、以前は菅生から離れた地域にも転々と小さな圃場を持っていたのですが、農機具を運ぶにもひと苦労ですし、何より移動にかかる時間がもったいない。そういった不便な圃場は整理して、大規模園芸団地に参入しました。これまでは小さな圃場をいくつも耕していましたが、今では広大な圃場に大きなトラクターを導入していちどに作業できるようになり、効率化が叶いました。団地内には大型のトラクターやトラックが離合できるほど広い農道も整備されており、2027年の事業完了までにかんがい施設の整備なども行われる予定なので、この先さらにメリットを感じられるのではないかと期待しています。

―― ほかの生産者さんたちとはどのようにコミュニケーションを取っていますか?
私以外にも、参入した個人の生産者が15名います。以前からよく情報交換はしてきたのですが、近年の気候下では今までの経験値が通用しなくなってきていますので、互いに知恵を出し合えるのは有り難いと思います。また、今回の事業が始まる前、土地を集約するにあたって皆で話し合い、大分県酪農振興公社の土地を中心にまとめ、個人の圃場は団地の両端に割り振ろうと決めました。今後、我々も高齢化して農業を辞めることになった場合、耕作放棄地となる土地をまとめられたら次の担い手に譲りやすいし、企業にも参入してもらいやすいのではないかと。将来を見据えてのことです。
【今後の展望】
次の世代に知識と技術を伝えるのが使命
―― 今後の課題は何ですか?
繰り返しになりますが、いつか私たちも引退する日が来ます。私の場合は息子が後を継いでくれていますが、どの家庭も同じ状況ではなく、若手人材は足りていません。そのため、「団地の整備事業が終わった10年後はどうなっているんだろう?」という懸念があり、今から次の世代を育てていかなければならないと切実に感じています。農家は決してラクな仕事ではありませんが、努力しただけ結果が返ってくる喜びがありますし、これだけ大規模な圃場ならスマート農業にも取り組めると思います。興味のある人は、ぜひ挑戦してほしいですね。

―― 大規模園芸団地への参入を検討している方々に、アドバイスをいただけますか?
先ほども触れましたが、区画整理の直後は、農地の水はけが変化することがあります。今後、団地への参入を目指す方は、造成後の排水管理が重要です。時間が経てば良くなる傾向にありますので、そういうケースがあるという前提で、取り組んでいただけると良いと思います。それに、何か問題や相談事があれば、大分県の担当の方がバックアップしてくれます。

―― 最後に、これからの目標を教えてください。
年齢的に、農業を続けられるのもあと10年くらいかもしれません。それまでに、長年農業に携わって得た経験を、若い人に伝えて人材を育てるのが使命だと思っています。
竹田市担当者の声)
造成後、圃場の排水が悪く、耕作者の皆さまに大変ご迷惑をおかけしました。排水の問題については、耕作者の皆さんからご意見をいただきながら大分県と連携して排水機能の改善に努めてまいりました。耕作者が2、3作する内に「排水が良くなってきた」との声をいただき、胸をなでおろしています。竹田西部3期地区は1区画の面積が非常に大きく、畑地整備のさきがけとなる事業です。当地区の整備により竹田市の農業がますます発展することを期待しています。