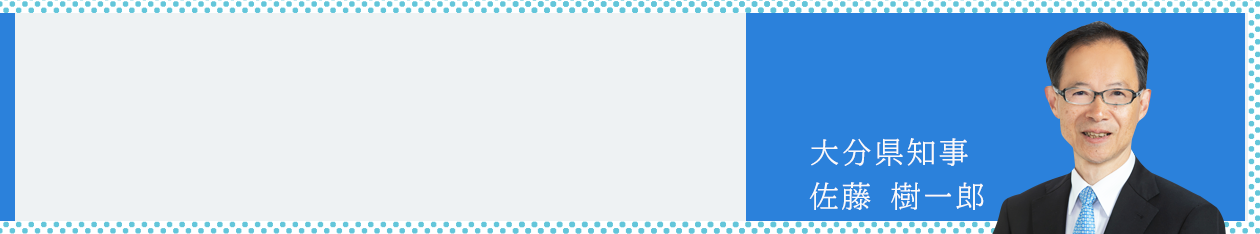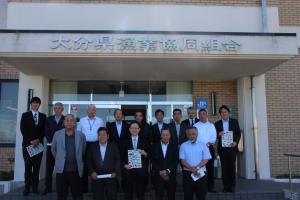本文
知事通信「県政ふれあい対話(5月14日:佐伯市)」
青山地域コミュニティ協議会(佐伯市)
佐伯市では、人口減少や少子高齢化に伴い、従来の「区」ごとの活動が困難になる将来を見据え、地域住民が自主的・主体的に地域課題に取り組み、住民福祉の向上及び地域の発展を図るため、地区公民館や市振興局単位でのコミュニティ再編を進めています。「青山地域コミュニティ協議(青山てらす)」は、その一環として、佐伯市でも高齢化が進んだ青山地区において、令和5年3月に設置された団体です。
発足に際しての議論では、どうしても年配の方に遠慮して若者からの意見が出にくいこともあったようですが、若者が中心となって地域のイベントを開催するなどの取組によって、徐々に地域に一体感が生まれ、現在では非常に良い関係となっているとのことでした。
懇談では、独自財源の確保策として、地域の特産である米を利用した焼酎や団子などの産品をご紹介いただくとともに、販売支援についてのご要望もお聞きしました。また、令和5年度末で閉校となった青山小学校について、能登半島地震においても課題となった「ペットと一緒に避難できる避難所」として活用できないかというご提案をいただきました。
協議会の皆さんから様々なアイディアをいただいたことに感謝を申し上げるとともに、今後とも青山地域を盛り上げ、引っ張っていってもらいたいとお伝えしました。
株式会社漁村女性グループめばる(佐伯市)
株式会社漁村女性グループめばるは、地域に住む3人の「浜のお母さん」が、魚をもっと食べて欲しいとの想いから平成16年に結成した団体で、郷土の調味料として親しまれてきた「ごまだし」等の加工販売に取り組まれています。
結成当初は活魚を販売していたそうですが、お客さんに魚をさばけない方が多かったことから、「口元まで運べる加工品」を作ろうということになり、地域の家庭で作られていた「ごまだし」に注目されたとのことです。「ごまだし」は、魚を焼いて身をほぐし、胡麻と一緒にすり合わせて醤油等を足して仕上げた調味料で、化学調味料や保存料などを一切使わないことが特徴です。その美味しさと安心感は各種品評会でも高く評価され、首都圏の大手スーパーでも販売されているほか、マスコミにも大きく取り上げられました。
後継者に事業承継してからは、春夏秋冬の旬の魚を使用した季節限定の商品によるブランド力向上に努めているほか、海外輸出も視野に入れ、保存期間の延長に挑戦しているとのことです。また、最近の原材料価格高騰の影響や食品安全基準の厳格化により屋外イベントへの出店が困難となっている状況などについてもお伺いしました。
皆さんの努力の結果、「ごまだし」が大分を代表する産品の一つとして世に広まったことに敬意を表し、これからも多くの人のために、新商品開発や販路拡大等に挑戦していただきたいとお伝えしました。
大分県漁業協同組合 県南地区漁業運営委員長会(佐伯市)
佐伯市はリアス海岸の複雑な地形と森や川がもたらす栄養塩により、多くの魚介類を育む豊かな海が形成されています。この環境により多種多様な海面漁業や養殖業が発展し、その生産量は県内の6割以上で、特にブリ類、ヒラメ類を中心とした養殖業は全県生産量の約7割を占めるなど、本県水産業の重要な拠点となっています。大分県漁業協同組合県南地区漁業運営委員長会は、平成14年に合併した大分県漁業協同組合に所属する佐伯市内8支部を束ねる委員長から構成されています。
懇談では、近年の地球温暖化等による漁業環境の変動によって漁獲量の減少や魚種・漁獲時期が変化している状況や、世界情勢の影響による燃料価格の上昇や養殖飼料価格の高騰により経営へ大きな打撃を受けている現状を伺いました。
海面漁業の対策としては、漁業者による資源管理や適地放流などの稚魚放流事業等を実施され、養殖業では、水質改善事業や避難漁場等の整備などに取り組まれているそうです。また、今夏には需要拡大へ向け、切り身などにも対応できる加工場が完成することもお伺いしました。
さらに課題として、藻場の整備や養殖用生餌への補助のほか、さらなる県独自の水産支援等について、ご意見、ご要望をいただきました。
漁業を取巻く現況や課題について改めて認識できたことに感謝を申し上げ、国や佐伯市とも連携して、引き続き研究や対策に取り組んでいきたいとお伝えしました。
大入島の活性化に取り組む皆さん(佐伯市)
佐伯湾に浮かぶ周囲約17キロメートルのひょうたん形をした大入島には、現在約500人が住んでいます。主要産業は漁業で、牡蠣の養殖のほか、ちりめんじゃこが名産です。島内には、「九州オルレ」のコースが設置されており、豊かな自然と景観を楽しむことができます。
かつて、住民が3千人以上もいた大入島ですが、人口減少や少子高齢化が進み、空き家が目立つようになったそうです。そこで、島をもう一度活性化させようと、韓国で人気であった「オルレ」の誘致活動に着手し、平成29年には、九州に2か所しかない「九州オルレ」として認定されました。その後の6年間で、韓国をはじめとする国内外からの累計参加者数が1万人を突破するなど、大きな反響を得ているそうです。
また、漁獲量が減少する一方であった漁業を活性化させようと、牡蠣の養殖に取り組み、オーストラリアなどで導入され省力化が可能な「シングルシード方式」を日本で初めて導入されました。綺麗な環境で育てられ長期輸送に耐えられる牡蠣は「大入島オイスター」として出荷され、大変好評とのことです。
一方で、人口減少により増加した空き家や校舎の利活用について、また、地域交通の確保等の課題についても、ご意見やご要望をお伺いすることができました。
島の活性化のため、さまざまな取組を行っていただいていることに感謝を申し上げるとともに、県も引き続き協力していきたいとお伝えました。