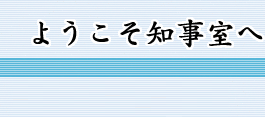
令和7年8月19日知事定例会見
動画はYouTube「おんせん県おおいた公式」へ
日時:令和7年8月19日(火曜日)13時30分~
場所:第一応接室
記者会見時に配布した資料を掲載します。

8月10日からの大雨の対応と災害への備えについて
8月10日からの大雨ですが、大分県西部でも、10日夜に線状降水帯が発生し、日田市では観測史上最大となる1時間117ミリの雨量が記録されました。
大分県では、災害警戒本部を設置して、情報収集等を行いました。
県内では、人的被害はありませんでしたが、現時点で日田市で12棟、玖珠町で3棟の住家被害が報告されています。そして現在も1名の方は日田市内のホテルに避難をしているという状況がございますので、被害に遭われた皆様には心からお見舞いを申し上げます。
昨日、私も日田、玖珠、九重と訪問しましたけれども、特に日田は中心市街地の方で、家屋が浸水したところもあったということを地域の皆様からお伺いしました。各市町と連携をしながら、引き続き復旧・復興に取り組んでいきたいと考えています。
また、7月30日にはカムチャツカ半島付近の地震により大分県でも津波が観測され、一昨日の8月17日には、県内で震度3の地震も観測されたところです。
このようなことから、やはり災害に対する備えというのは、常に怠らずやっていく必要があるということで、8月30日から9月5日の防災週間に合わせて防災グッズフェアを行う予定です。
防災グッズフェアは、8月25日から9月7日までの2週間、県と協定を締結している企業8社72店舗において特設コーナーを設置し、保存食などの非常持出品や家具の転倒防止のためのグッズなどの展示・販売を行います。
県民の皆様には、改めて家具の固定ですとか、非常時の持ち出しリュックなどの点検をお願いできればと思います。
次に、鶴見岳の火山防災訓練です。6月以降、鹿児島の新燃岳の噴火活動も続いていますが、大分県にも3つの活火山がありまして、8月26日の「火山防災の日」に合わせて、鶴見岳が噴火したことを想定し、避難誘導などの訓練を行います。
昨年は幸いなことに災害で亡くなられた方はいらっしゃいませんでした。今年も今のところいらっしゃらないということで、県民の皆様には、引き続き自分の命、家族の命を守るため、「備蓄」「早めの避難」、そして自分の安全を確保した上で周りの方への「声かけ」の取組を、ぜひ実行していただきますよう、改めてお願いいたします。
配 布 資 料:今しちょかんと、まにあワン・・・ 防災グッズフェア チラシ [PDFファイル/558KB]
令和7年度鶴見岳火山防災訓練(概要) [PDFファイル/270KB]
おおいた産業人財センターの移転について
本県では、産業人材の確保に向けた取組をより一層強化するため、ガレリア竹町にある「おおいた産業人財センター」を、9月1日に、大分駅ビル・アミュプラザおおいた内へ移転します。
「おおいた産業人財センター」では、県内外の求職者に対する支援や県内企業の人材確保の支援等を行ってきておりますけれども、移転に合わせ、県内企業と若者が気軽に交流できるスペースを設置するほか、人材確保に関する専門アドバイザーを設置し、県内企業へのコンサルティング支援を行います。また、外国人の雇用に関する企業向けの相談窓口も開設します。このように、さまざまな課題に対応できる体制を整えて、人材確保の総合支援拠点としての役割を担っていきたいと考えています。
新しい施設の愛称は「おおいたジョブステーション」ということで、大分駅内にあることが分かりやすく、仕事と出会う場所としての役割が伝わる親しみやすい名称としました。シンボルマークも作りまして、求職者の方が、挑戦する前向きな姿を、背中を押す「追い風」で表現することで、信頼感や安心感が感じられ、新しい第一歩を踏み出す勇気を後押しするようなデザインとなっていますので、ぜひこの「おおいたジョブステーション」を活用いただきたいです。
配 布 資 料:おおいた産業人財センター移転リニューアルについて [PDFファイル/401KB]
「宇佐神宮御鎮座1300年 おおいた“よりみち”スタンプラリー」等の実施について
今年は、宇佐神宮御鎮座1300年の記念すべき年であり、これを契機としたさまざまな行事が行われています。これまでも、5月には将棋の名人戦がありましたし、7月末には御神幸祭などが行われています。今後も10月6日には10年に一度、勅使を迎える臨時奉幣祭(勅祭)が行われるほか、26日の時代祭では歴史装束をテーマにした時代絵巻行列が開催されるなど、重要な行事が予定されています。
県では、こうした取組をさらに盛り上げるべく、県内の歴史や文化を感じることができる観光スポットを巡るデジタルスタンプラリーを9月1日から11月30日までの3か月間実施します。
スマートフォン等を利用し、県内50箇所に設置したスポットに行くと、そのスポットをイメージしたオリジナルデザインのデジタルスタンプが貯まる仕組みとなっています。
貯まったスタンプ数に応じて、さんふらわあ乗船券や、特産品の詰め合わせなどの商品が当たる抽選に応募することができます。より多くのスポットを巡るほど豪華賞品を獲得するチャンスが増えますので、ぜひスタンプラリーを楽しみながら、大分県の魅力を堪能していただきたいと思います。
なお、デジタルスタンプラリーと並行して、御鎮座1300年を契機とした観光バスツアー「大分ゆめバス」も8月1日から実施中です。こちらも活用して、多くのお客様に県内を周遊してもらいたいと思います。
配 布 資 料:宇佐神宮御鎮座1300年(後半)イベント チラシ [PDFファイル/622KB]
宇佐神宮御鎮座1300年おおいたよりみちスタンプラリー チラシ [PDFファイル/2.83MB]
ホーバーターミナルを活用したにぎわいづくりについて
空港アクセス便の就航から約1か月が経ちまして、順調に利用をいただいており、特にお盆休みなどは、周遊の方はほぼ満席の状態が続いていましたし、空港アクセス便もかなり多くの方々に使っていただいています。
そしてホーバーターミナルは、大阪・関西万博の大屋根リングの設計者であります藤本壮介さんの設計ということで、ある意味で西大分の魅力の1つになってくるのではないかと思いますし、別府湾の景観になじむ、大変魅力のある建物です。こうしたポテンシャルもあり、新たな交通結節点となるこのエリアはにぎわいの創出が期待されています。
8月9日から18日の間には、物産展やホーバー見学会などを開催し、多くの方々で賑わいました。周遊便も増便し、連日満席近い運航になったと聞いています。
そして来月9月13日にはかんたん公園で開催される、「みなとのフードフェスタ2025」にあわせ、ホーバーターミナルも会場にして、キッチンカーの出店や縁日イベントなどを行います。浜の市奉納花火大会もありますので、ぜひお越しいただき、ホーバーターミナルの雰囲気のなか、別府湾の夜景と花火も楽しんでいただければと思います。
ホーバーターミナルは、今後もいろんなイベントに活用可能ですので、県民の皆さんにご提案いただきながら、活用いただければと思います。ぜひご利用くいださい。
配 布 資 料:みなとのフードフェスタ2025 チラシ [PDFファイル/1.21MB]
令和7年度一般会計9月補正予算案(第2号)について
9月の第3回定例県議会に提案する補正予算案がまとまりましたので発表します。
今回の補正予算案では、賃金と物価の好循環の創出に向け、賃上げや人手不足対策に必要な経費を計上するとともに、安心・元気・未来創造ビジョン2024の実現に向けた取組を推進することとしています。また、令和6年度決算剰余金を財政調整用基金等に積み立てます。
まず補正額は、108億3,378万4千円の増額であり、補正後の累計は、7,139億2,722万4千円となります。
財源は、歳入の内訳のとおり、国庫支出金が15億608万4千円であり、うち重点支援地方交付金が1億6,729万7千円となっています。
次に、繰入金として、ふるさとおおいた応援基金の取崩しが2億5,000万円、令和6年度決算剰余に伴う繰越金が、90億7,770万円となっています。
次に、補正事業の内容について、まず(1)賃上げと人手不足対策についてです。
1つ目は中小企業等業務改善支援事業3,750万円です。これはまだ審議会で検討中ではありますが、おそらく本県の最低賃金は1,000円を超える水準になってきます。このような中で生産性向上による持続的な賃上げの実現を図るため、中小企業等に対する県独自の上乗せ支援である業務改善奨励金を拡充するものです。具体的には、本県の最低賃金改定幅を超えて賃金を引き上げた中小企業等を対象とした重点枠を新たに設け、補助率を1/2から2/3へ、限度額を75万円から100万円に拡充します。
2の労務単価の上昇を踏まえた委託料の増額ですが、契約後の想定を上回る大幅な労務単価の上昇に対応できるよう、県発注の委託業務に労務単価の上昇に応じて変更契約を可能とする賃金スライド制度を導入するとともに、必要額を計上するものです。
3の医療提供体制緊急支援事業5億5,059万5千円は、人口減少や人手不足の影響により医療機関の経営が厳しさを増す中、引き続き地域の医療提供体制を確保するため、病床数の適正化や機能分化に取り組む医療機関を支援するものです。
4の農業担い手確保・育成対策事業7,280万2千円は、農業者の生産性向上や規模拡大を図るため、ニーズ調査やスマート農業機械の導入経費の助成など農業支援サービス事業体の立ち上げを支援します。
5の地域あんしん給油所推進事業2,790万円は、地域の見守り、ガソリン価格の店頭表示、観光客へのおもてなしに取り組む給油所を「地域あんしん給油所」として登録する制度を新たに創設し、その推進に必要な設備整備に対して助成するものです。
続いて(2)「安心・元気・未来創造ビジョン2024の推進」のための事業です。
6の入院小児患者付添い環境改善事業1,878万円は、入院中のこどもに付き添う家族が休息できるスペースを確保するため施設改修等に取り組む医療機関を支援するものです。
7の畜産収益力強化対策事業7億600万円は、地域内連携による畜産経営体の収益力向上を図るため、畜舎等の整備を支援するものです。
8の再造林促進事業2億5,000万円は、森林所有者による主伐後の再造林を推進するため、ソフトバンク株式会社からいただいた寄附金を活用し、早生樹による再造林等を支援するものです。
9から11は、令和6年度決算剰余金を活用し、今後のビジョン2024の推進に必要な財源を確保するため、芸術文化基金に8,000万円、企業立地促進等基金に10億円、おおいた元気創出基金に19億3,644万2千円を積み立てるものです。
その他に、条例に基づき決算剰余金の3分の1相当額の30億2,593万4千円を財政調整基金及び減債基金にそれぞれ積み立てることとしています。
今回の積立てにより、9月末時点での財政調整用基金残高は約306億円となりますが、行財政改革推進計画2024の目標である330億円の確保に向け、引き続き、歳入確保や事業の節約等に努めてまいります。
以上が、補正予算案の概要です。
配 布 資 料:令和7年度一般会計9月補正予算案(第2号) [PDFファイル/634KB]
令和6年度普通会計決算見込みについて
次は令和6年度の決算の見込みについてです。
まず、「歳入・歳出及び収支の状況」についてですが、物価高に伴う生活支援や事業者支援のほか、豪雨災害からの復旧・復興などに取り組んだ一方、新型コロナ関連経費が大幅に減少したことなどにより、歳入・歳出規模は3年連続の減少となりました。また、歳入・歳出の差から、翌年度繰越財源を除いた実質収支は、91億円の黒字となっています。
次に、「財政の健全性」についてです。財政構造の弾力性を示す「経常収支比率」は、人件費や公債費などの増により経常経費が増加したものの、県税収入の増等により経常一般財源も増加したことから、昨年度から0.2ポイント増の92.3%となりました。また、実質公債費比率など財政健全化4指標は、いずれも早期健全化基準を下回っています。
最後に、「安定的な財政基盤の確保」ですが、財政調整用基金残高は、331億円と3年連続で目標額330億円を確保でき、県債残高総額も臨時財政対策債の償還が進んだことなどにより1兆517億円と3年連続で減少しました。実質的な県債残高は6,153億円と前年度から30億円増加しましたが、交付税措置のない県債の発行を抑制し、6,500億円以下という目標水準を堅持したところです。
他方、今後も官民を通じた賃上げによる人件費や外部委託費など、更なる財政需要の増加が見込まれます。引き続き、行財政改革推進計画2024に基づく取組を着実に実行し、持続可能な財政基盤の確保に努めてまいります。
普通会計決算見込みについては以上ですが、補正予算案と併せ、この後に担当課の方から説明をさせていただきます。
配 布 資 料:令和6年度 普通会計決算見込みの概要 [PDFファイル/361KB]
令和6年度大分県普通会計決算見込みについて [PDFファイル/2.95MB]
記者質問
8月10日からの大雨の対応と災害への備えについて
(記者)
線状降水帯が発生した8月10日からの大雨が激甚災害に指定される見込みとされたが、それを受けた県の今後の動きは。
(佐藤知事)
今回は、この大雨による災害が激甚災害に指定される見込みですので、これから、土木や農業施設の復興など、さまざまな予算もかかってきますし、いろんな取組が必要になってきますから、国の補助率が嵩上げされますので、活用していきたいと思います。
ただ、ある一定額以上の被害がないと対象にならないこともあるので、どの程度の活用となるかは被害状況を確認し、精査しています。
(記者)
今回の大雨による被害額は。
(佐藤知事)
住家被害以外の、例えば農業とか土木はもう少し時間がかかると思います。まだ調査中です。
(記者)
もし概算でもあれば伺いたい。
(農林水産部審議監・土木建築部審議監)
農地・農業用施設等は、8月18日時点で152件、約5億円、公共土木施設は、8月14日時点で51件、約12億円の被害状況となっています。まだ調査中ですので、今後変動することがあります。
(記者)
知事として、どこから重点的に支援していく考えか。
(佐藤知事)
被害を受けたところすべてです。どこが一番早くということではなく、それぞれしっかりやっていかないといけないと思います。
令和7年度一般会計9月補正予算案(第2号)について
(記者)
「地域あんしん給油所推進事業」について、この事業を始める経緯や背景は。
(佐藤知事)
給油所は地域の見守りの拠点として、非常に重要な役割を占めています。これまでも、例えば、帰り道がわからなくなった方や、こどもの見守りをやっていただいている給油所がたくさんあります。
もう1つは、ガソリンの価格について、大分県は他県と比較して高いのではないかというお話もありまして、全国で言うと、おそらく10番目ぐらいになっていると思います。価格は国際的な動きによっても変わってきますが、価格表示をしていないガソリンスタンドが非常に多いということで、これはできるだけ表示をするように県からも要請しています。
一方で表示をするにあたって費用がかかるという指摘もありますので、今回のように認定した方が取り組みやすいのではないかという議論をしまして、予算化をしようと考えた次第です。
(記者)
いつから始まる見込みか。
(佐藤知事)
議会で補正予算案を可決いただいてから可及的速やかに始めたいと思っています。秋頃からと思います。
(記者)
ガソリンスタンドが地域の見守りの役割を担っているのは、どういった取組で、いつ頃からなのか具体的に伺いたい。
(生活環境部審議監)
大分県石油商業組合で、「安心・安全ステーション」という取組を行っており、こどもの見守り、あるいは、災害時の支援活動などを行っています。
(記者)
県の最新の調査ではガソリンの価格が表示されているのが4割弱という数字があるが、この実態について知事の所感は。
(佐藤知事)
県では65%の目標を掲げていますので、目標値より低いことから、要請もしているところです。価格設定はスタンドによってさまざまな事情もあると思いますが、価格をできるだけ表示してもらった方が消費者の方々も良いと思います。価格表示板も補助金の対象になりますので、この施策を契機として、さらに価格表示を行うスタンドが増えてくることを期待しています。
(記者)
価格表示板の補助は、店頭表示するための設置や、そのための改修費用を補助するということか。
(佐藤知事)
はい。要請したときに、費用がかかるとの声も聞こえてきていますので。
日出生台演習場における陸上自衛隊員の訓練中の死亡案件について
(記者)
自衛隊の玖珠駐屯地で、お二人の隊員が亡くなられたという事案について、今回は、小銃等を持っていなかったということであるが、行方不明になったのは一昨日である。対してマスコミには昨日の夜19時頃に情報提供があったようである。
こうした銃火器を持つ可能性のある陸上自衛隊の隊員さんが、行方不明になったという情報を、知事、もしくは県の担当部署が把握したのは何時頃か。
(佐藤知事)
まず、陸上自衛隊のお二人が訓練の最中に死亡されたということに対しまして、心からお悔やみを申し上げたいと思います。
死亡原因をしっかり特定をしていただいて、再発防止に努めるということが大事なことかなと思います。
ご質問の点ですが、消防組織法の定めから火災・救急事案の一部は、消防本部から県を通じて消防庁に報告するとなっており、その過程で、一報を昨日8月18日の午前7時24分にFAXで受信しています。その後19時25分頃、九州防衛局から「19時15分に記者クラブ宛てにプレスリリースした」という連絡が改めてありました。
(記者)
県として最初の情報は午前7時24分に入っているとのことであるが、どのような内容か。
(防災局防災危機管理監)
内容は、玖珠駐屯地の中で、隊員が心肺停止になっているという救急車の要請事案があるという程度です。
(記者)
国の防衛にあたられている方たちとはいえ、武装をする人たちでもあると思うが、7時24分時点での報告について、遅い早いなど知事自身の受け止めは。
(佐藤知事)
県としても対応しようがない事案のため、遅すぎる、早すぎるといった評価はしようがないかなと思っています。
(記者)
当初、消防本部から情報を得たとのことであるが、陸上自衛隊の方から県に報告はあったか。
(佐藤知事)
九州防衛局から19時15分に記者クラブ宛てにリリースしたとの連絡が19時25分にありました。
(記者)
リリースしたという報告ですが、事案について詳しい状況は把握できたのか。
(佐藤知事)
おそらく九州防衛局も死因がわかっていないので、それ以上対応のしようがないのだと思います。死亡原因は調査中ということで連絡がありました。
今のところは、報道されていることと同じような範囲での情報提供はありましたが、それ以上のことについては、おそらく九州防衛局においても、調査結果を持っている状況ではないでしょうか。
(記者)
県としても、報道されている程度の情報は報告を受けたということでよろしいか。
(佐藤知事)
はい。
(記者)
今後もそんな情報共有を求めていく姿勢はあるか。
(佐藤知事)
県の行政を行う上で必要な情報かどうかは当然あると思いますので、住民の安全やさまざまな不安の解消など、そういうことに必要な情報は、当然求めていきたいです。
観光客の動向について
(記者)
7月の観光動態調査において、外国人宿泊客が前月比で25%減少しているが、原因についてどのように考えているか。
(佐藤知事)
大分空港のチェジュ航空便が昨年比で減便になっていますので、その影響と、大阪・関西万博が開催中であることや、沖縄県にジャングリア沖縄が開業するなど、そういった方面への旅行需要が増していることも、複合的に影響してきているのではないかと思います。海外からの宿泊客については特にチェジュ航空便の減便が大きく効いているかなと思います。
また、7月5日に大地震が起きるといった漫画の影響も、原因の一つとして考えられると思います。せっかく旅行に行くのであれば、そんなデマのないところが良いと思った人たちが多かったのではなかろうかという声は聞いています。デマも含めてさまざまなことが、実経済に影響してくるんだなと改めて感じているところです。
大分トリニータの監督交代について
(記者)
大分トリニータの片野坂監督の契約解除が昨日発表されたが、J2で16位と低迷している状況も踏まえて県としての所感は。
(佐藤知事)
まず、片野坂監督には2度にわたって大分トリニータを率いていただいて、1回目の時には天皇杯の準優勝もありましたし、それからJ3からJ1まで上がっていったのも、片野坂監督の力も大きかったと思います。今までの貢献に対して心から感謝を申し上げたいと思います。
また、J2残留についても、なんとか踏ん張って、そこからJ1を目指して、頑張ってもらえるような体制を作ってもらいたいと思っています。
ダムの貯水率について
(記者)
北部地域では、農業用ダムの貯水率が回復していない地域もあると思うが、どのように考えているか。また、先日、土地改良区の皆さんも要望に来られたと思うが、何か対策を考えているか。
(佐藤知事)
いろいろご要望もあるので、要望を踏まえながら検討していかないといけませんけども、先日の雨で、貯水率もかなり回復してきておりまして、宇佐市の香下ダムも少し節水をしていただければ、なんとか持ちこたえられるという状況になっていると認識しています。
稲刈りまでの間、水が保たれれば良いため、節水について引き続き協力をしていただければと現時点では考えています。
今後、高温により水が予想以上に減ってくることもあるかもしれませんので、臨機応変に対応していこうと考えています。
(記者)
今の時点で何らかの支援を行う予定は。
(佐藤知事)
状況も見ながら、必要があればもちろん躊躇なく行っていきます。
夏の甲子園について
(記者)
夏の甲子園で明豊高校が3年ぶりに初戦突破し、3回戦では接戦により惜しくも敗れたが、明豊高校の戦いぶりについて、知事のコメントをいただきたい。
(佐藤知事)
大変、健闘していただいて素晴らしい試合を3試合とも見せてもらったと思います。3試合目も明豊高校の方がチャンスはあったんですけど惜しかったですね。
ベスト16となりましたけど、もっと次の試合を見たいと思えるようなチームづくりをしてくれたな思います。
自民党総裁選について
(記者)
参院選の結果を受け、臨時で総裁選をするのかという意見もあるが、知事として所感は。
(佐藤知事)
自民党の総裁を選ぶというのは、自民党の中のプロセスですので、私として特段の意見はありません。
最低賃金について
(記者)
全国で最低賃金の協議が進んでいる中、一部で赤沢大臣が直接、各都道府県知事に要請するような動きもあると聞くが、県内ではいかがか。
(佐藤知事)
ありません。
(記者)
今回の予算でも最低賃金引上げを後押しするような予算を組んでいるが、知事の姿勢として、賃金上昇に向けての考えは。
(佐藤知事)
人材を確保していく上で、賃金上昇は必要だと思いますし、賃金と物価の好循環を実現していくことが大事だと思います。一方で、中小企業の方や、農業関係者などに話を聞くと、エネルギー費が上がっているなか、人件費も上げていかないといけないが、売上がなかなか伴わないとも聞いています。
そういう意味で、最低賃金が上がっても、どうやって賃金を上げれば良いか悩んでいる経営者が多いというのが実情です。それを少しでも後押しするための施策として、補正予算案でも2分の1の補助を3分の2に引き上げようとしていますし、賃上げ枠というのも12項目設けていますけど、そういうのも広げられるところはないかなというのは検討したいと思います。さまざまな形で、少しでも賃上げができるような環境整備をやっていきたいと心がけています。
(記者)
特に中小零細企業の賃上げの難しい方々にアプローチする方針か。
(佐藤知事)
そうですね。あとはもちろん、政労使会議もありますし、賃金、価格転嫁の円滑化などに、引き続き取り組んでいきたいと思います。
県政ふれあい対話について
(記者)
昨日「県政ふれあい対話」で、日田・玖珠方面に行かれたということで、天ヶ瀬の地域は令和2年の豪雨から5年の節目ということだが、復興の状況や、地域の方々の声を聞いていかがか。
(佐藤知事)
県政ふれあい対話も3年目に入って、100を超える団体を訪問し、これまでに800人近くの方とさまざまな意見交換をさせてもらいました。
まず総論としては、やはり各地で取組をしている県民の皆さんの声や意見、それから県政に対する要望を直接聞いて仕事を進めていくというのは、改めて大変重要だなと思います。地域の活性化や高齢化地域での支え合い、地域医療をどう支えていくか、農林水産業や工業、観光といった分野でどのような取組や工夫をしているか、そうしたことについて多くの声をいただけます。
昨日も日田観光旅館組合の皆さんや、天ケ瀬の方々と意見交換をしましたが、その時に、7、8、9月と観光客がすごく落ち込んで、10月くらいから回復する見込みという話を聞きました。そういう傾向があるとは聞いていたのですが、実際に生の声としてお聞きできるのは大きいですね。
天ヶ瀬では、令和2年の大洪水からの復旧で令和8年から工事に入るわけですが、川底に温泉の泉源があるため、普通の災害復旧工事のように川底を深く掘ることができません。したがって、川幅を広げていくしかなく、そのためには両側の旅館の方々にセットバックしていただくような大工事が必要になります。加えて、現在架かっている橋をどう扱うかなど課題も多く、県にとっても大きな事業になります。
そうしたなかで、今回の訪問では、未来予想図をどう描いていくのか、もっと示してほしいという声もいただきました。まさに天ヶ瀬温泉の未来を考える上での工事となるため、旅館の皆さんの意見や心配事を直接伺えたのは大事ですし、こうして現地に出かけて、時間をいただきながらお話を聞いたり提言をいただいたりするのは、本当に貴重な機会だと思います。
また、昨日はそれぞれの市長さん、町長さんや職員の皆さん、地域選出の県議会議員も一緒に参加してくれていましたので、県と市町村が連携しながら、また議会とも共有できる場になっていると感じています。
こうして100団体以上への訪問を積み重ねてきて、もちろん準備や日程調整など、多くの方に集まっていただくことは大変な面もあると思いますが、我々にとっては行政を進める上でとても貴重な機会になっていますので、引き続き、こうした取組を続けていきたいと思います。
(記者)
本来この取組の趣旨は、意見や提言を県政に反映させるということで行われていると思うが、これまで実際にどういったものが反映されているか。
(佐藤知事)
大きなものというよりは、一つひとつの困りごとを共有していくことが大事だと思います。
例えば高齢化の地域では、昔は地域の方が木を切ったりして対応できていたのが、今はなかなかできなくなっていて、「木の枝が伸びて車がこすれて危ないんです」といった声がその場で出てきたりします。
また、「まちおこしのための予算がもう少しあるといい」という声もあって、古民家の再生やまちづくりに関する要望もいただきます。
先ほど申し上げたように、市長さん、振興局、土木事務所の職員たちも一緒に参加してくれていますので、できることはその場でやっていこうと共有しながら進めています。
それから、出てきた意見や提言は他の地域でも共通することがあるので、冊子にまとめています。
例えば剪定の予算額は、ご意見を伺った翌年からおよそ3倍に増やすことができました。1つずつきめ細かな施策にはなるかと思いますが、改善も進めています。
別府では「歴史的な建物がどんどん壊されている」とまちづくりの皆さんから声がありました。そこに支援できないかという提言をいただき、それを受けて総合補助金の制度を改正しました。
訪問先も幅広く、福祉施設や障がい者の方々の施設、農林水産業の現場などさまざまです。こうして多岐にわたる現場からいただいた提言を、施策として取り入れていけるところを取り入れるようにしてきました。その結果、県の施策自体も改善されてきたと思います。
おおいたスペースフューチャーセンターについて
(記者)
おおいたスペースフューチャーセンターが解散する方向と一部報道されたが、知事は把握されているか。またその受け止めや、今後の県の宇宙関連事業の見通しへの影響はあるか。
(佐藤知事)
解散の話を私は直接お伺いしておりません。担当課から会員が減ってきていることを理由に解散になったと聞いています。
宇宙産業はこれからも伸びていく産業だと思いますので、これまでも宇宙教育でありますとか、関係のベンチャービジネスの振興などに力を入れています。引き続き取組を行っていきたいと思います。




