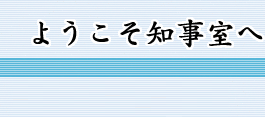
令和7年6月17日知事定例会見
動画はYouTube「おんせん県おおいた公式」へ
日時:令和7年6月17日(火曜日)13時30分~
場所:第一応接室
記者会見時に配布した資料を掲載します。

梅雨時期における災害への備えについて
6月8日に平年より4日遅れて梅雨入りし、いよいよ本格的な出水期に入りました。
出水期に備え、4月から5月にかけて県管理の堤防のある153河川、約377km、土砂災害警戒区域235箇所、山地災害危険地区37箇所、防災重点農業用ため池1,021箇所、農業用水路311箇所の事前点検を実施し、2箇所で応急措置を実施しました。
また、6月6日には関係機関との連絡手段や対応手段を確認するため、58機関300名が参加する防災訓練を実施しました。引き続き、災害への備えに万全を期していきます。
梅雨に入ったばかりですが、すでに2回の大雨警報が発令され、一部地域では避難指示も出されました。県民の皆さんには、何よりも大切な早めの避難をお願いします。まずご自身の命を守り、ご家族の命を守ってください。そして、周りの方にも気を配り、「備蓄」、「早めの避難」、「声かけ」を実行していただくよう、改めてお願いいたします。
配 布 資 料:なし
大分県災害中間支援組織の設立及び協定締結式について
能登半島地震の際、NPOの受け入れに時間がかかり、ボランティアの受け入れが一時停止されたことをご記憶の方もいるかと思います。こうした経験を踏まえ、来週24日(火)に、大分県における災害中間支援組織として「おおいた災害支援つなぐネットワークO-Link(オーリンク)」が民間団体により設立されます。
翌25日(水)には、県とO-Link、そして全国からの支援をコーディネートする「認定NPO法人全国災害ボランティア支援団体ネットワークJVOAD(ジェイボアード)」の三者による連携協定を締結する予定です。
O-Linkの役割は主に2つあります。1つ目は、県内で局所的な災害が発生した際に、各避難所等のニーズと専門ボランティアとのマッチングを行うことです。2つ目は、南海トラフ地震などの大規模災害発生時に、全国から駆けつけるボランティアの受け入れ窓口として調整を担うことです。
現在、県内の高齢者やこどもの支援、炊き出しのノウハウなど専門的な知識を持つ約20の団体がこのO-Linkに加入する予定であり、心強く思っています。
特に大規模災害発生時には、行政の支援が行き届きにくい被災者のニーズに対応するため、社会福祉協議会や関係機関と連携しながら、O-Linkの強みを活かして活動することになります。その活動により、被災者一人ひとりに、きめ細かな支援が行き渡り、災害からの早期復旧、避難所での災害関連死防止、そして生活再建につながることを期待しています。
配 布 資 料:大分県災害中間支援組織の設立及び協定締結式について [PDFファイル/718KB]
大分県災害中間支援組織の設立について [PDFファイル/273KB]
男女共同参画の推進について
毎年6月23日から29日までの1週間は「男女共同参画週間」です。職場、学校、地域など様々な場所で男女共同参画社会を実現するための取組が行われますが、今年度は「誰でも、どこでも、自分らしく」をキャッチフレーズに進めていきます。
23日(月)には、関係機関と協力し、大分駅前広場で街頭啓発キャンペーンを実施し、男女共同参画を呼びかけます。
また、「アイネス男女共同参画フェスタ2025」を6月28日(土)に予定しており、映画「弁当の日」を上映します。この映画は、弁当をつくるという小さな実践がこどもの成長を後押しし、周りの大人を変えていくことを描いています。上映後には、元西日本新聞記者で「はなちゃんのみそ汁」の著者でもある安武信吾監督による講演会も開催します。当日は、豊かな人生の送り方や子育て応援などのワークショップやパネル展もありますので、これらの企画を通じて男女共同参画について改めて考える機会としていただければと思います。
また、女性が輝き活躍できる社会づくりも重要です。令和5年度から、女性が働きやすい職場づくりや女性登用に積極的な企業を「女性活躍応援県おおいた認証企業(おおいたキャリエール)」として認証する制度を実施しており、この2年間で71社を認証しています。
さらに今年度からは支援措置を拡充し、おおいたキャリエール認証企業に対し、応援補助金として、職域拡大や労務環境改善を進める際の事業費の半分(上限160万円)を支援することにしています。これは15社限定で、審査もありますが、先着順としています。
女性に選ばれる魅力的な職場づくりに取り組む企業を、引き続き応援していきますので、ぜひご活用ください。
配 布 資 料:男女共同参画週間 チラシ [PDFファイル/379KB]
アイネス男女共同参画フェスタ チラシ [PDFファイル/571KB]
女性活躍応援県おおいた認証企業 チラシ [PDFファイル/229KB]
おおいたキャリエール補助金 チラシ [PDFファイル/277KB]
「おおいたにじいろ講演会in由布」について
毎年6月は「LGBTプライド月間」であり、世界各地で性的少数者の権利啓発イベントが行われています。大分県でも、性の多様性について県民一人ひとりの理解を深めるため、講演会などを開催しています。
今年は、由布市と共催で「おおいたにじいろ講演会」を由布市庄内公民館大ホールで開催します。6月26日(木)に、トランスジェンダー当事者である遠藤まめたさんをお招きし、ご講演いただきます。LGBTQの基礎的知識や講師ご自身の経験、そしてこども・若者支援を通じて見えてきた現状と課題についてお話しいただく予定です。
後日、録画配信も行う予定ですので、多くの方々にご視聴いただければと思います。多様な性に対する理解と共生社会について考える機会となることを願っています。
配 布 資 料:おおいたにじいろ講演会 チラシ [PDFファイル/325KB]
令和7年度 高校生向け合同企業説明会について
7月1日(火)にクラサス武道スポーツセンターで高校生向けの合同企業説明会を実施します。若者の人口が減少する中で、高校卒業生の県内就職者の確保は、今後の県経済を支える上でも重要な課題です。また、就職する側にとっても、県内に多くの魅力的な企業があることを知り、将来にわたって幸せな職業人生を送ることなどを考えるよい機会になると思います。
現在、高校卒業生の約75%が県内企業に就職しており、これは九州でも福岡県に次ぐ割合です。しかし、高校卒業生は、5年前と比較すると、令和2年3月が1,878名であったのに対し、令和6年3月は1,521名と、約350名減少しています。このため、企業側は求める人材の確保が難しい状況にあります。
この説明会は今回で14回目となりますが、県内企業の魅力を高校生に知ってもらい、県内就職につなげるための取組です。今年は過去最高の232社が参加し、2,300名を超える高校生に参加いただく予定で、高校生の皆さんには、ご自身にぴったりの、ここで頑張ろうと思える企業を見つけていただきたいですし、企業の皆さんには、それぞれの会社の魅力を存分に発信し、人材確保に役立てていただきたいと思います。
配 布 資 料:令和7年度 高校生向け合同企業説明会について [PDFファイル/239KB]
記者質問
大分県災害中間支援組織について
(記者)
組織を設立した理由は、また全国的に先進事例はあるか。
(佐藤知事)
全国的な流れも進んでいます。特に能登半島地震の際に、NPOやボランティア団体の受け入れ体制が整っていなかったため、一時的に現地入りを待ってもらうようアナウンスせざるを得なかった経緯があります。しかし、ボランティアの方々がいち早く現地に入って活動することは、きめ細かな対応をするためにも非常に意義があることだと思います。
現在、全国的にもこのような受け入れ組織を整備する動きが進んでおり、すでに23の都道府県で災害中間支援組織が設立されています。こうした動きは今後もさらに広がると思われますので、それが災害時にしっかりと機能する体制を整えることは非常に重要だと考えています。
(記者)
現在の大分県の防災対応における弱点や課題をどのように考えているか。また、この支援組織がその解決にどうつながると考えているか。
(佐藤知事)
現在、県と市町村、消防団や防災士などさまざまな団体が連携しています。要支援者のリストアップについても、自治会や民生委員、児童委員の協力を得ています。しかし、今回O-Linkに参加する予定の20団体との連携はまだ十分にできていない部分がありました。例えば、日田市のNPO法人リエラさんは、これまでも行政と一緒になりながら、能登半島地震にも支援に行ったり、その支援経験を県が行うセミナーで話してくれたりしています。ただ、いろんな団体としっかりネットワークを構築し、お互いに情報共有を行い、一緒になって取り組むところまではまだできていないという課題があり、これは全国どこでもそうだと思います。O-Linkの設立により、これらの連携の中核を担ってもらうことを期待しています。
また、南海トラフ地震のような大規模災害が発生し、県内が壊滅的な状況になった場合には、佐賀県が職員を派遣して応援してくれることになっていますが、全国から駆けつけてくれるNPO団体やボランティアの方々の受け入れを調整する体制がなかったので、O-Linkが設立されることは、非常に有効だと考えています。
(生活環境部審議監)
これまで避難所への支援物資の提供や被災家屋の泥出しといったボランティア活動については、社会福祉協議会が中心となって調整していました。災害中間支援組織では、例えば避難所での高齢者やこどもの生活支援など、専門知識を持った専門ボランティアの方々にしかできないきめ細かな支援について、受け入れ窓口として調整を担っていただくことになります。行政の手が届きにくい部分にも、専門ボランティアによる支援を届けることにより、これまで以上に一人ひとりの命を助けていけるようになるものと考えています。
(記者)
この組織に対する期待は大きいということか。
(佐藤知事)
はい、大変期待しています。
女性活躍認証制度について
(記者)
2年間で71社を認証したとのことだが、これは2年前から始まった制度か。また、今年度、補助金などで拡充された点は。
(佐藤知事)
制度は2年前から始まりました。補助金については、6月9日から募集を開始したばかりで、まだ実際の応募はありません。
この制度は、まず「おおいたキャリエール」の認証を受けていないと補助金を利用できない仕組みになっています。そのため、まずは認証に応募していただき、その後この補助金を活用して事業を進める企業が増えることを期待しています。まだ制度を知らない方も多いかもしれませんので、報道を通じて多くの方々に周知していただきたいと思います。
(生活環境部審議監)
募集期間は6月9日から8月29日までです。審査もありますが、予算の範囲内で先着順となるため、予定より早く募集を締め切る場合があります。興味のある方はお早めにお申し込みください。問い合わせも多数いただいておりますので、皆様ぜひPRをお願いいたします。
(佐藤知事)
先着順の部分もありますので、早めに相談や応募をしていただけるとありがたいと思います。
(記者)
女性活躍が進むことで、こどもを産み育てやすい環境にもつながり、人口減少対策の鍵にもなると思うが、知事のこの分野に対する思いは。
(佐藤知事)
まず、女性が活躍できる分野が大きく広がっているという点が挙げられます。
例えば、「BLOCKS」という建設産業における女性活躍を推進する事業があります。その事業では、女性の建設業従事者と中小企業の社長、そして工業高校や大学で建設・土木を学ぶ学生が集まり、女性の活躍に向けて意見交換が行われています。
女性が活躍できるようになった理由の一つは、ITや機械の発展です。これまで男性でなければできなかった建設現場の仕事も、ITや機械の活用により女性が十分にこなせるようになりました。設計や様々な機械操作も、今や女性が十分に操れるようになっています。
もう一つは、仕事内容の変化です。これまでは専門技術を持った人が黙々とそれぞれの作業を行い、チームワークがそれほど重要ではなかった建設現場でも、現在は住民への説明やチーム内でのコミュニケーションが重視されるようになっています。こうしたコミュニケーション能力は女性が秀でている部分が多く、この点においても女性が活躍できる余地が広がっています。
中小企業の社長も、これまで活躍してくれた女性を評価していて、ぜひ続けてもらいたいと言われています。そのためには、女性が働きやすい職場環境を整えることが重要です。産休をしっかり取れるようにし、復職後も産休や育休がハンディにならない職場を作ることで、せっかく頑張っている女性が離職しないようにする、という社長の言葉もありました。このように、女性の活躍の場はますます広がっています。
これは一例ですが、あらゆる分野で女性が活躍できる場は広がっており、それがこどもを産み育てたいという希望につながっています。父親と母親が共に子育てをする社会に変えていくことも必要です。そのような社会になれば、こどもを産み育てたいけれど将来が不安だというのではなく、それならこどもを育てようと考える人が増えると思います。働きやすい職場づくりにより、いろいろな障壁があったものが取り払われ、全体として少子化社会からこどもを育てることが素晴らしいという社会に変わっていくことにつながると思います。
広い意味で言えば、それぞれの希望が叶えられる社会になります。高校生へのアンケートでは、男女ともに8割以上が将来結婚を希望しているという結果もあります。現状は、希望がなかなか叶えられていない若者が多いということだと思います。働きやすい職場づくりの取組を通じて、こうした状況を少しでも改善していきたいと考えています。
参議院議員通常選挙について
(記者)
特定の候補者を支援される考えはあるか。
(佐藤知事)
特定の候補者を支援するつもりはありません。
(記者)
次の参議院議員選挙は国政の今後を占う上でも重要な選挙だと思うが、知事として、選挙戦を通じて期待している議論はあるか。
(佐藤知事)
やはり地方創生の議論がどう進むかに注目しています。骨太の方針が閣議決定され、その中には広域交通ネットワークやDXの推進、教育などさまざまなテーマが盛り込まれています。
例えば、新幹線の基本計画路線の扱いは、さらなる取組を進めるということで、昨年よりも一歩踏み込んだ記述になっています。
地方創生を進める上で、昨年は、デジタル田園都市国家構想でしたが、今年は地方創生という表現に変わり、リアルとデジタルの両面を含む議論が進みつつあると思っています。こうした議論がどのように展開されるか注目しています。
特に、地方創生が、骨太の方針の中で一丁目一番地の扱いになっていると思います。その論戦がどう行われるか、注視していきたいです。
(記者)
自民党が参議院選挙の公約で現金給付を打ち出しており、物価高対策とする一方で、ばらまきという批判の声もあるが、知事としてこの現金給付政策を率直にどう見ているか。
(佐藤知事)
現金を給付するよりも、重点的な日本の将来を形成する大事なところにしっかりと投資をするという使い方、投資と現金給付の財源は違うと思いますので、さまざまな議論があるとは思いますが、やはり地方創生に資するような予算の使い方をしてもらった方がありがたいというのが率直な意見です。
(記者)
投資するというのは、具体的にこういう使い方の方が良いという考えがあるのか。
(佐藤知事)
例えば、広域交通ネットワークの整備は投資的経費にあたります。建設国債発行の話にはなるでしょうが、そういう整備をどういうふうに進めていくかというための調査とか、そういうようなことが将来の日本にとっては大事なのではないかと思います。
もう一つはやはり教育です。教育もまた、将来に対する投資と言えます。先々週、政府予算等に関する要望活動を行いましたが、その際も現在進めている遠隔教育について要望しました。今年度は4校を対象として、9名の教員で配信をスタートしましたが、遠隔教育の教員の配置については国費支援の対象外となっていますので、支援対象に含めてもらうよう要望しています。
DXの推進や教育の重要性は骨太の方針にも明記されていますから、大分県で進める遠隔教育の取組に対しても、予算措置を講じてもらえるとありがたいと思います。
(記者)
現金給付が選挙対策なのではないかという批判もあるが、その点はどう見ているか。
(佐藤知事)
その点はよく分かりません。
実際に実施されるのは年内か年末、少なくとも選挙よりも後になるでしょう。困っている人々を支援するという政策は、新型コロナウイルスの際にも度々ありました。ですから、物価高で困っている人々を支援しようという政策はもちろん理解できます。ただ、それがすべての人に当てはまるわけではないのではないかと感じます。
(記者)
与党から現金給付の話がある一方で野党からは減税案が出ているが、知事の所感は。
(佐藤知事)
減税についても、社会福祉や地方財政にどのような影響を与えるのか、といった様々な影響をしっかり比較検討しなければなりません。
そして、どの部分を減税するのか、安定財源の部分か、景気によって大きく変動する部分なのか、さらにそれが何に充てられているかといった用途の部分もしっかり考慮していかないと、大事な施策ができなくなってしまうと本末転倒になります。
これらの点を、政府税制調査会や党税制調査会など、与野党でしっかり議論して、国民的コンセンサスを形成して進めていってほしいと思います。
(記者)
現金給付と減税案でしたら、知事としてはどちらの方が良いか所感は。
(佐藤知事)
それは内容によると思います。先ほど少しお話ししましたが、一律にすべて現金給付を行うようなやり方は、個人的にはどうかなと思います。
困っている人々に限定した給付や、例えば渡しきりの奨学金の拡充など教育関連のような給付など、様々な現金給付の方法がありますので、内容によって検討されるべきでしょう。減税についても同様で、消費税、所得税、法人税、ガソリン税など、それぞれ効果や影響が異なります。一律に減税すべきだあるいはやめるべきだと判断するのではなく、一つひとつ議論していく必要があると考えています。
(記者)
減税案では、食品に対する消費税を軽減するなど、さまざまな案が出ているが、知事として所感は。
(佐藤知事)
減税、つまり税のあり方としては、まずシンプルな税制が良いと思います。
また、応能負担と応益負担のバランスをよく考える必要があります。すべて応益負担ということではないと思います。ある程度収入の多い人には、社会への還元という意味で応能負担も重要です。このバランスをどう考えるかですね。
またもう一つは目的税があります。先日、東九州新幹線等を整備計画路線にするために、九州地方知事会で出国税の活用を提案しました。現在、日本人、外国人を問わず、日本を出国する際に1,000円が課税されていますが、この税額を上げて、増収分を新幹線整備に充ててはどうか、というものです。
この出国税は、インバウンド観光客が日本国内をストレスフリーで快適に旅行できる環境を整備するための財源として使われることになっています。新幹線が整備されれば、例えば大分県や宮崎県にも新幹線が延伸すれば、外国人観光客の移動がスムーズになりますので、出国税の目的に沿うものですから、新幹線の整備に活用してもよいのではないかというものです。
非常に似たものに宿泊税があります。これは県や市町村が独自に課税できるもので、別府市でも現在検討されています。宿泊者から追加で税金を徴収し、その地域の観光整備に充てるというものです。大分県でも、観光振興のためにはそのような財源が必要ではないかという検討を始めたところです。
このように、目的税は、その目的と合致した徴収方法であるか、そして何よりも納税者の賛同や理解が得られるかどうかが重要です。
(記者)
現金給付か減税かというところでは、知事としては、どっちがいいというところではなく、現金給付であれば、全体に押しなべてというよりは困っているところに届く、かつ、減税であれば、目的が明確で使い方がはっきりしているというものがよいという考えか。
(佐藤知事)
そうですね。
(記者)
特定の候補者は応援しないとのことだが、改めて知事の政治姿勢やその考え方を。
(佐藤知事)
今回の参議院選挙は全県一区であり、県民の皆さんの選択です。そのため、県民一人ひとりの一票の行方を見守ることが私の基本的な姿勢だと考えています。
私自身は無所属であり、そのような立場からも、特定の候補者を応援するのではなく、選挙全体の動向を注意深く見守りたいと思います。
(記者)
一方で、候補者からは知事への応援要請があるかと思うが、現時点で特定の政党や陣営からの応援依頼、演説、メッセージなどのアプローチはあるか。
(佐藤知事)
現時点では、そういったアプローチはありません。
(記者)
今後、そうしたアプローチや依頼が来た場合、どのように対応されるか。
(佐藤知事)
まだ依頼が来ていないので、具体的には考えていません。要請があればその時に検討したいと思います。基本的にはニュートラルな立場でいることを考えています。
備蓄米について
(記者)
県内での流通状況や平均価格など、把握している情報はあるか。
(佐藤知事)
県内のスーパーマーケットなどでも備蓄米が棚に並び始めています。6月4日には日田市内のドラッグストアで、6月12日には大分市内のディスカウントストアで販売が開始されました。また、6月14日からはコンビニエンスストアなどでも販売されています。
価格については、全国の販売価格は6月2日から8日の期間で4,176円/5Kgと、前の週から48円下落しています。
(農林水産部審議監)
県内の状況は、基本的に国の傾向と大きく変わらず、県内でも価格は下がってきています。
(佐藤知事)
正確な数字については、改めて取材でご確認いただけると助かります。
(記者)
銘柄米を含めた平均価格も全国と同じくらいの水準ということか。
(農林水産部審議監)
全国では4,176円/5Kgです。県内の数値はありません。
(記者)
小泉農林水産大臣が昨日、作況指数を廃止するとコメントしたが、知事の受け止めは。
(佐藤知事)
比較もありますので、あまり性急に変更しない方が良いと思います。これをベースにこれまでの農政の検討もされています。統計や農業の専門家の意見をよく聞きながら、性急に何でも変えるのではなく、必要な検討を経て、変えるべきところは変えていくのが良いのではないでしょうか。
(記者)
現在の政府の対策は少し性急だと見ているということか。
(佐藤知事)
現時点で、報道されている情報しか知りませんので、具体的なスケジュールや意図について、私自身が正確な情報を持ち合わせていないため、断定的なコメントはできません。
台湾便の就航状況について
(記者)
台湾便の就航からまもなく2か月が経つが、搭乗率は好調に推移しているか。
(佐藤知事)
基本的には好調に推移していると思いますが、タイガーエア台湾は非常に高い搭乗率、100%に近い数字を期待しており、もっと搭乗率を上げてほしいと思っているようです。状況によって、今後の冬期の運航を継続するのかどうかの判断にもつながると思います。
県としては、好調ではありますが、タイガーエア台湾の期待に応えるためにも、さらに多くの方々に大分-台北便をご活用いただきたいと考えています。現在運航している国際線、チェジュ航空とタイガーエア台湾の両方をぜひ維持していきたいというのが正直な気持ちです。
(記者)
台湾から大分に来る観光客は好調だと伺っているが、県民の利用は伸び悩んでいるのではないか。
(佐藤知事)
おっしゃるとおりです。台湾から来る方々は、現地の旅行会社がパック商品を販売しているため、大分を訪れ、その後ほかの地域へ向かうなど、魅力的な旅行商品を通じて来県される方が多いです。
一方で、大分から台湾へ出発する日本人、特にビジネス目的の利用者は、自身のスケジュールを優先する傾向にあります。現在の運航スケジュールである水曜日と土曜日にぴったり合えば大分空港を利用しますが、合わない場合は福岡空港を利用するケースが多いです。そのため、台湾からのインバウンドに比べて、大分からの利用は低調なのが実態です。
しかし、便がなくなると非常に不便になるため、県民の皆さんにも、多少スケジュールを調整してでも大分発の便を利用するなど、ご協力いただけるとありがたいです。
(記者)
大分発の便は夕方に出発する便であり、不便だという声もあると思うが、運航会社との間でスケジュールの変更に関する調整や要望はあるか。
(佐藤知事)
具体的な要望が運航会社から来ているわけではありませんが、やはり搭乗率を高めるための工夫はできないかという話は出ています。今お話ししたようなことも含め、今後さらに工夫の余地があると考えています。
(記者)
11月以降の就航継続に向けては県民の利用促進が重要だと思うが、現在取り組んでいることや今後取り組んでいきたいことはあるか。
(佐藤知事)
ぜひ大分空港発の便をご利用くださいという働きかけを、機会あるごとにお願いしていきたいと思います。具体的な施策については、これから交通政策局と検討を進めていきたいと思います。
人口動態調査と少子化対策について
(記者)
先日発表された人口動態調査で、県内の新生児数が初めて6,000人を下回ったとことに対する受け止めは。
(佐藤知事)
思った以上に人口減少、特に自然減が進んでいると思います。最も多かった時は年間42,000人程度の出生数があったことを考えると、現在は7分の1近くまで減少しています。
結婚された方々が何人のこどもを持つかという有配偶者出生率を見ると、高い水準にあります。
そのため、結婚したいのに出会いがない、あるいは将来の収入増加の見込みが少なく結婚を躊躇しているといった方々への対策が重要だと考えています。これなら結婚して家庭を持とうと思えるような環境づくり、賃金と物価の好循環の賃金上昇の話もあると思います。
また、出会いの場を増やすことも重要で、先日も県主催の婚活イベントを知事公舎で行いましたし、今度はホーバークラフトを活用した婚活イベントも行う予定です。いろんな場で出会いの場を作っていきたいと思います。
さらに、市町村やメディアの皆さんにも協力いただき、さまざまな出会いの場を創出していただいています。昔はお見合いの世話役がいましたが、そうした役割を担う人がいなくなっていることもあります。
もう一つは、こどもを持つことや子育ては人生において大きな喜びであるというメッセージを改めて発信していくことも重要だと思います。
ホーバークラフトの就航状況について
(記者)
もうすぐ夏休みシーズンに入り、多くの観光客や帰省客が訪れることが想定されるが、就航に向けた最新の状況はどうか。
(佐藤知事)
報告を受けている範囲では大きく変わっていませんが、私自身の感触としては、これまで二つの大きなハードルがあったと感じています。
一つ目は、操縦の難しさです。操縦士の熟練度をどう上げていくかが課題でした。二つ目は、船体の整備力です。ホーバークラフトが安定して運航できるよう整備力を高めることがもう一つのハードルでした。当初の定期就航予定からは1年以上遅れていますが、この期間をかけて、この二つのハードルをクリアできるところまできているという感触があります。
何とかこの二つのハードルをクリアし、安全を確保して定期就航を実現したいと考えています。別府湾周遊便はすでに4,500名を超える方にご利用いただいており、1回30分の周遊ですが、ゴールデンウィーク期間中などは非常に好評で、満席になることもありました。私自身も乗船しましたが、風が穏やかな日だったこともあり、ホーバークラフトが滑るように走り、別府湾やコンビナートの素晴らしい景色を堪能できました。
時間はかかっていますが、この二つの難しいハードルをクリアできるのではという期待が高まっているところです。
(記者)
定期就航の便数が当初の計画から減便され、その代わりに訓練時間を確保するという一部の報道について、知事は把握しているか。また、便数を減らしてでも訓練時間を確保することについて、知事の所感は。
(佐藤知事)
安全性が何より重要だと考えています。大分第一ホーバードライブによる当初の発表時から、夜間便は別途検討するなどとアナウンスがされていたのではないでしょうか。
先ほど申し上げたとおり、操縦や船体の整備については少しずつハードルをクリアしていますので、ある意味で、小さく始めて、安全を確保しながら便数を増やしていくというやり方は当然あると思います。
便数が減ることが後退をしたということではなくて、むしろ定期就航をまずスタートして、運航をする中で自信をつけ、さらに安全性を高めていくということであれば望ましいやり方だと思います。
おそらく、県も大分第一ホーバードライブも、当初の就航便数については公表していないと思いますが、安全が確保できるのであれば、そのような進め方は大いにあり得ると思います。
骨太の方針について
(記者)
骨太の方針に関して、新幹線のさらなる検討を行うという部分に言及され、前向きに捉えているとのことであるが、改めて、その部分の文脈の確認と具体的にどのような点を前向きだと捉えているのか。
(佐藤知事)
幹線鉄道ネットワークに関する記述については、「各地域の実情を踏まえ、地方創生2.0の実現にも資する幹線鉄道の高機能化に関する調査や方向性も含めた検討など、更なる取組を進める。」と書かれています。
「更なる取組を進める」や、「幹線鉄道の高機能化に関する調査や方向性も含めた検討」といったことが書かれており、昨年よりも一歩踏み込んだ表現になっています。毎年チェックしていますが、少しずつ前向きな表現になっているのは確かです。
一方で、財源が限られているという現実も認識しています。この中で、どのように工夫して進めていくかは、引き続き全国知事会などで議論していかないといけないと思います。
(記者)
「幹線鉄道の高機能化」というのは、中速の新幹線などを指しているのか。
(佐藤知事)
その意味については、国土交通省鉄道局に確認しないと分かりません。新幹線というと、250km/hで走行するものを思い浮かべますが、例えば130km/h程度で走行するミニ新幹線など、新幹線と同等の機能が果たせるようなものを指している可能性もあります。いろんなことを研究しないといけないと言われる専門家や国土交通省の方々もいます。その意味合いについては確認が必要ですが、そういうことも入っているかもしれません。
(記者)
東九州新幹線と、そうした中速の新幹線がリンクしている説明ではないのか。
(佐藤知事)
確認はしていませんが、「基本計画路線を含む幹線鉄道ネットワークについて」という記述から始まっているので、既存の新幹線とは異なるあり方について議論があるのかもしれませんし、ないのかもしれません。これは私の推測なので、正確には再度確認が必要です。
しかし、2週間前に国土交通省の審議官や鉄道局長と話をしましたが、そこまで具体的な議論は進んでいないというのが実態ではないかと思います。例えば、西九州新幹線のように解決策を見いだせていない路線や敦賀-大阪間の小浜ルートか米原ルートかのルート問題、北海道新幹線の遅れなど、現在の整備新幹線自体が足踏みしている状況です。
これらの既存の整備計画路線の問題が解決しないと、次の整備計画路線の議論は難しいのではないかと思います。しかし、このまま待っているだけでは、基本計画路線に指定されてからすでに50年以上が経過しているように、さらに時間がかかってしまいます。そういう意味では、九州地方知事会で議論したようなことをやりながら乗り越えていく、財源確保を含めて進めていかないとなかなか動かないというのが、今のところの私の実感です。
(記者)
今回の骨太の方針には財源確保については盛り込まれていないが、知事の考えは。
(佐藤知事)
全国知事会などで議論を進め、賛同する仲間を増やしていくことが重要だと考えています。
(記者)
今回の骨太の方針における「更なる取組を進める」という表現を、知事としては成果と考えているか、もっと踏み込んだ文言を期待されていたか。
(佐藤知事)
その点については、表現は前向きになっていますが、これだけではやはり進まないという思いもあります。そのため、今後は全国知事会なども含めて、さらにさまざまな取組をしていかないと、進まないなと思っています。
地方創生2.0基本構想について
(記者)
骨太の方針と同時に閣議決定された地方創生2.0基本構想についての受け止めは。また、その中に「若者や女性にも選ばれる地方をつくる」という文言が盛り込まれているが、大分県としてどのように若者や女性に選ばれる県としていきたいか。
(佐藤知事)
先ほど説明した高校生向けの合同企業説明会のように、県内にある素晴らしい中小企業についてもっと知ってもらうような取組もありますし、地方創生を進める上で、若者や女性が次の原動力になると思いますので、そうした方々に選ばれるような取組は大事になってくると思います。
そして、石破総理が「楽しい日本」という話もされていますが、その視点も非常に大切だと私も思っています。大分県には魅力のある楽しい地域、世界に誇れるものがたくさんあります。大分でないとないものとして、例えば、アルゲリッチ音楽祭や国際車いすマラソンのほか、APU(立命館アジア太平洋大学)のような日本でも類を見ない留学生の多い大学などもあります。
魅力のある地域づくりが地方創生につながってくると思います。魅力のある地域は、住んでいて楽しく、訪れて楽しい地域だったりするわけです。大分ハローキティ空港もそうですし、サンリオの屋外型テーマパークは世界で大分にしかないわけです。こうした大分ならではの魅力を作り、ここに来ると楽しい、あるいは住んでいると楽しいと感じてもらえるような地方創生を進めることが、一つの道だと考えています。
これは人口の自然増減だけでなく、社会増減にも大きく影響する部分です。そうした点にしっかり取り組んでいきたいと思います。




