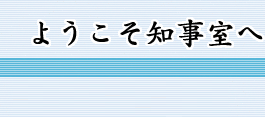
令和7年1月21日知事定例会見
動画はYouTube「おんせん県おおいた公式」へ
日時:令和7年1月21日(火曜日)14時00分~
場所:第一応接室
記者会見時に配布した資料を掲載します。

大分県政労使会議の開催について
国においては、昨年11月26日に政労使の意見交換を開催し、総理から直接、経済界及び労働界に対し、物価上昇を上回る構造的な賃上げについて協力を要請したところです。
これを受けて、現在、全ての都道府県において、賃上げの流れが地方にも波及するよう、「地方版政労使会議」が開催されています。
本県におきましては、お配りしている資料のとおり、大分労働局との共催により、「大分県政労使会議」として、来週1月31日(金)に開催いたします。
この会議には、大分県内の労使の代表のほか、国から九州経済産業局長、公正取引委員会九州事務所長にも御参加いただきます。
当日は、「賃金引上げに向けた取組」をテーマとして意見交換を行い、政労使が一体となった新たな共同宣言を発出する予定です。
本会議を通じて、生産性の向上や適正な労務費の価格転嫁等を含めた物価上昇を上回る構造的な賃上げの機運醸成を図ってまいります。
昨年も大幅な賃金上昇はあったものの、実質賃金を見れば物価上昇が勝っている状況が続いていますので、引き続き政労使で合わせて、賃上げの機運醸成を図っていくということが大変重要だということでこの会議を予定しております。
配 布 資 料:大分県政労使会議の開催について [PDFファイル/1.2MB]
構造改革特別区域計画申請について(大分県立工科短期大学校から大分大学理工学部への編入学)
1月6日に、内閣府へ、大分県立工科短期大学校から大分大学理工学部への編入学のための構造改革特別区域計画の認定申請を行いました。
工科短大は、本県産業を支える実践技術者の育成などを目的に、職業能力開発短期大学校として設立された2年制の学校です。厚生労働省所管の学校であるため、これまでは文部科学省所管の4年制大学への編入学は認められていませんでしたが、今回の申請が認定された後には、編入学が可能となります。
この特区を活用することで、工科短大に入学した学生が編入学を希望し、大分大学で実施される編入学試験に合格すれば、大分大学理工学部に編入学できます。
今後は、工科短大の魅力を高校生などに発信するとともに、編入先となる大分大学とも連携することで、高度な技術力に加え研究開発能力やマネジメント力を備えた、地域産業の発展に資するイノベーション人材の育成に繋げてまいります。
なお、工科短大では、令和7年1月6日から2月5日までの期間で、一般入学試験の願書を受け付けていますので、ぜひこれを機に応募していただきたいと思います。
今後のスケジュールに記載のとおり、令和7年3月末頃に内閣府から認定をいただき、令和7年度中に編入学試験を行い、令和8年4月から編入学が開始できるように準備を進めておりますので、ぜひ認知いただいて工科短大に進学する学生さんが増えてもらえればと思っています。
配 布 資 料:大分県立工科短期大学校から大分大学理工学部への編入学について [PDFファイル/102KB]
おおいたスタートアップ・クリエイティブマンス2025について
県では、年間創業支援件数700件を目標に各種セミナーや販路拡大、県内外の先輩起業家とのネットワークづくりなど、さまざまな創業・スタートアップ支援に取り組んでいます。
お手元にパンフレットをお配りしていますが、特に、毎年2月を中心とした約1か月間を「スタートアップ・クリエイティブマンス」と位置づけ、創業やクリエイティブに関するイベントを集中的かつ一体的に実施しています。
お手元のパンフレット、7ページをご覧ください。2月12日(水)に、大分県ビジネスチャレンジコンテスト「OITAゼロイチ」を開催します。県内外53名の応募者の中から、1次審査を通過したファイナリスト10名が、ビジネスプランを発表し、最終審査の上、各賞の受賞者が決定されます。
次に、11ページをご覧ください。2月26日(水)には、スタートアップ5社によるピッチイベント「Oita(オオイタ) GROWTH(グロース) Ventures(ベンチャーズ) DEMODAY(デモデイ) 2025(ニーマルニーゴー)」 を開催します。ビジネスで社会課題解決を目指す起業家たちが、プログラムの成果や事業成長に向けてのプラン等を発表します。
こうした取組を通じて、引き続き、スタートアップ支援やクリエイティブの活用に努めるとともに、起業を目指す人材の発掘にも繋げてまいります。
配 布 資 料:おおいたスタートアップ・クリエイティブマンス2025について [PDFファイル/3.78MB]
大分県建設産業女性活躍加速化促進事業成果発表会「BLOCKS FUTURE LOUNGE」の開催について
大分県建設産業女性活躍加速化促進事業ということで、成果発表会「BLOCKS(ブロックス) FUTURE(フューチャー) LOUNGE(ラウンジ)」を開催いたします。
建設産業に女性の力をということをキーワードにして、令和2年度から建設産業で活躍する女性の方々の活動、活躍の推進に取り組んでいます。積み上げるというイメージでBLOCKS(ブロックス)と呼んでいます。
今まではトップリーダーのセミナーや女性技術者の技術知識を身につけるスキルアップセミナー等を行ってきました。
また、報道もしていただきましたけども、建設産業で活躍する女性と、そういうところで活躍したいと思い勉強している高校や大学工学部の女子学生さん、そういう方々の交流会を知事公舎で行いました。
その時には、先輩方から、今まで建設業は男性の職場だったけども、機械がどんどん入って女性が活躍できる余地が増えたということ、もう1つは、この産業というのはコミュニケーション能力が必要になってきているということを言っていまして、例えば道路を作るにしても建物を作るにしても、地域住民の皆さんにしっかり説明しながら進めていかないといけない。職人の方が黙々とやっていくようなイメージがあったのですけど、今はチームでやっていかなきゃいけないということで、仕事をする仲間同士でも、コミュニケーション能力が大変重要になってきていますと。そういうことから女性が活躍する可能性というのは大いに高まってるんですよって話を、先輩方がされてまして、勉強している女性の方々も目を輝かせて聞いたり質問したりしていました。
建設業の社長さんも参加をしていまして、その人は男性でしたけども、活躍している女性が得難い人材であるので、例えば妊娠出産があったときは一旦離れますけど、そのあとしっかり戻ってきてもらえるように、例えば女性の更衣室とかトイレとかそういうところもしっかり整備をして、社内の環境を整えていきたいというようなお話されていました。非常に熱心に参加された方々が意見交換していました。
今回のブロックスフューチャーラウンジは、2月1日にホテル日航大分オアシスタワーで開催します。学生や保護者など多くの方に参加いただき、セミナー受講者によるプレゼンテーションとか建設産業についての意見交換などを行い、建設産業の魅力について、身近に感じていただくという予定にしております。
1例でありますけども、やはり製造業とか建設業というのはどちらかというと、男性が中心のイメージ、例えばコンビナートなんかもそうです。
女性が活躍すると産業全体が元気になります。この発表会はよい取組だと思いますので、ぜひ多くの皆様に参加をしていただければと思います。
配 布 資 料:大分県建設産業女性活躍加速化促進事業成果発表会 「BLOCKS FUTURE LOUNGE」の開催について [PDFファイル/1.07MB]
記者質問
大分県政労使会議について
(記者)
来年度の当初予算の編成が佳境に入っている中で、物価高を上回る賃金上昇の機運を醸成するために今後考えられている施策等はあるか。
(佐藤知事)
現在検討中の段階ですので、改めてご説明をさせていただきますけれども、やはり賃上げ枠についてはさらに充実をしていくということを考えたいと思います。
本年度の施策で融資の保証料を免除した新たな融資制度を創設しました。また、厚生労働省の雇用・労働業務改善助成金に対して、大分県が上乗せで補助を行っています。そうしたものをさらに利用促進できるように周知徹底をしていくということをまず進めていきたいと思います。
加えて価格転嫁のところがまだまだ不十分だという状況もありますので、あらゆる施策を動員しながら、賃上げをさらにしやすい環境づくり、特に実質賃金が上がっていくような施策を推進していきたいと考えています。
大分県立工科短期大学校について
(記者)
特別区域計画申請が必要となる背景や取組により期待される効果は。
(佐藤知事)
まず人材不足が特区申請の背景となっており、特に製造業の分野で人材確保が難しいということが言われています。そういう意味でこうした工業系の、ものづくり系の人材を育成するというのは大変重要な課題となっております。
一方で工科短大は定員割れの状態が続いています。これまで、機械システム系、電気・電子システム系、建築システム系に私も伺い、見学をしたり、学生と意見交換を行ったりしましたが、ある意味で、大学の工学部と遜色ないような授業が2年間で行われていまして、大変高度なよい授業が行われています。
従いまして、まず工科短大に進学し、将来的には大学の理工学部で勉強したいと考えている学生にとって、工科短大は魅力的な選択肢となります。
工科短大は、高専と同じように、旋盤を動かしたり、さまざまな実技を学びながら理論も学べる場としての役割を果たしてきました。そうしたニーズに応えながら、より研究分野に取り組みたい、あるいは理論を深く学びたいと考える学生が大学に進学できる道をひらくコースを設けることで、工科短大に進学することの魅力をさらに高めていきます。
そして、これにより、高度なものづくりを担う人材の育成を進め、ものづくり分野における人材不足への対応を図っていきたいと考えています。
(記者)
近年九州において半導体も着目されているが、その対応も含まれているのか。
(佐藤知事)
もちろん、そういった点も踏まえています。半導体分野では人材が不足しており、九州全体で人材育成に取り組むことが重要でして、これは九州知事会などでも進められていますし、各工業高校、高専、大学の工学部でも、そうした人材の育成に力を入れています。さらに、台湾からも必要に応じて台湾の現地でオン・ザ・ジョブを含めた実践的な訓練を行うといった話があります。こうした取組の一環として、まずは基礎的な工学系の技術をしっかり身につけることが重要です。そのための教育を、こうした場で進めていくことになります。
人材不足の問題は、半導体分野に限った話ではなく、ものづくり全般でも深刻になっています。特に大企業では人材不足が顕著で、県が実施した500社企業訪問調査でも、規模が大きい企業ほど人材が不足しているとの結果が出ています。
そうした課題にしっかり対応していくことが重要です。
(記者)
資料にあります大分大学のプログラムはこのために新たに作ったものか。
(佐藤知事)
大分大学にはこのようなプログラムがあり、工科短大を修了した学生は編入の道があります。ただし、自動的に進学できるわけではなく、大学に入る際には編入試験が課されます。その試験に合格すれば、次のステップに進める仕組みになっています。
他県の例を見ても、すでにいくつかの地域で同様の取組が進んでいます。熊本、長野、山形、神奈川の4県はすでに特区として認定されており、例えば、今年度、山形県では山形県立産業技術短期大学から山形大学へ2名が合格し、神奈川県立産業技術短期大学ではこの2月に編入試験を実施予定です。長野県立工科短期大学からは、諏訪東京理工大学に1名が合格、熊本については今年度合格なしとのことですが、昨年度は1名が合格しているとのことです。
(記者)
工科短大からの大分大学の編入規模はどのくらいを想定か。
(佐藤知事)
今の1年生63名にアンケートを行ったところ16名ぐらいの方が編入学を希望すると回答しております。ただし、編入試験がありますので、ニーズは十分にあったとしても、他県の実績をみると1名とか2名程度の数名の結果となっていますが、募集人数は今のところまだ定まってはいません。
(商工観光労働部審議監)
大分大学が文科省と協議して、定員を何名とするかはこれから決めるということになると思います。
(記者)
大分大学理工学部の編入試験の要綱を見ると、今のところ3年次編入しか要綱にないが、こちらに合わせて2年次編入という枠組みを新たに設けるということか。
(佐藤知事)
そうですね。今、特区の認可認定申請を行ったので、それは並行しながらやっていくということだと思いますけど、一応2年次に編入するということで協議をしています。
米国大統領について
(記者)
アメリカでトランプ大統領が就任したことにより、例えば、宇宙産業や、輸出、国防・防衛など、トランプ大統領就任に伴う大分県への影響をどのように考えているか。
(佐藤知事)
いろんな施策を新たに打ち出されておりますので、これからということではあろうかと思いますが、米国は、大分県にとって農林水産物の重要な輸出先となっています。例えば、2023年の米国向け輸出額は約5.9億円で、そのうち養殖ぶりが3.3億円、牛肉が1.9億円と大きな割合を占めています。さらに、お酒やお菓子なども、国別では米国が最も多く、加工品についても米国向けが2.7億円、中国向けが2.3億円と大きなマーケットとなっています。
現在、米国で関税をかける議論が進んでおり、大分県の輸出にどのような影響があるかは不透明ですが、動向を注視し、今後の展開を見極めながら対応していくことが求められます。
(記者)
農林水産物を中心に大きなマーケットということだが、すでに牛肉など関税もかかっている状況で、トランプ氏就任による関税の影響で、輸出が落ち込む懸念やその不安感はどのように考えているか。
(佐藤知事)
関税の影響については、全体的な政策の中での議論となるため、まずは全体の動向を注視することが重要です。何よりも、日米が引き続き安定した関係を維持することが大切であると考えています。
その上で、個別の経済や産業への影響については、ひとつひとつ丁寧に議論を進めていく必要があります。関税の問題は国レベルでの議論が不可欠であり、例えば中国の漁業に関する輸出規制についても、国として意見を伝えている状況です。
私自身も、福岡の総領事との意見交換の際に、処理水の問題について早期の対応を求めました。ただ、関税の問題は基本的に国と国との交渉になるため、引き続き国レベルでの議論が重要であると考えています。
(記者)
またいわゆる台湾有事というようなことへの影響をどう考えているか。
(佐藤知事)
安全保障上の問題は、やはりどういう影響があるかをしっかり注視するということに尽きると思います。
これからどういう施策が打ち出されてくるかわかりませんので、世界を平和の方向に向けてということはメッセージとしてあると思いますので、そういうことを念頭に置きながらしっかり、これからの施策を注視していくということだと思います。
(記者)
自動車産業への影響をどのように見ているのか。
(佐藤知事)
日本の自動車産業にとって、アメリカ市場は非常に重要な存在です。過去の自動車貿易摩擦の際には、米国が輸出規制を行ったわけではありませんが、日本政府に自主規制を要請しまして、当時の自主規制台数は確か185万台でした。その結果、日本車の供給が制限され、アメリカ国内での価格が上昇し、中古車の価格も高騰しました。一方で、オハイオ州やミシシッピ州などにおける現地生産が進み、次第に米国内での生産が増加しました。
現在、米国内での生産拡大への投資は基本的に歓迎される傾向にあると考えられますが、今後同様の動きが出るかは不透明です。そのためには、鉄鋼をはじめとする高品質な素材の供給が不可欠であり、日本製鉄の投資の動向、政府の対応が注目されています。優れた素材がなければ、高品質な車を生産することはできないため、総合的な政策パッケージが検討される可能性があります。
現時点では、例えば大分のダイハツ九州の生産に直ちに影響が及ぶ状況ではないと考えられますが、今後の動きを注視していく必要があります。特に、自動車業界は100年に1度の大転換期と言われる変革期にあり、EV化の推進やハイブリッド車の戦略など、各メーカーがさまざまな戦略を検討している状況かと思います。
南海トラフについて
(記者)
先日、日向灘を震源とする地震があり、南海トラフ巨大地震の30年内発生確率が80%程度に引き上げられた件について、率直な受け止めは。
(佐藤知事)
大分県内では、大分市と佐伯市が震度4でしたが、揺れましてですね、大変ひやっとしましたけどもおさまりましてよかったなと思います。今まで70~80%だった予想が80%程度に上がりましたので、南海トラフ地震の本震がきた際に、しっかり対応できるような、そういう防災の準備、災害対応の準備をさらに進めていかなければならないというのが、受け止めです。
(記者)
簡易トイレの備蓄等を増やす対策など行っているが、今回の地震を受けて、より具体的に、取り組みたい方策等はあるか。
(佐藤知事)
今すぐ対応するということではありませんが、令和7年度の新規予算に向け、さらに災害に強いまちづくりをしていきたいと思います。
(記者)
発生確率が80%に引き上げられたことを受けて、県内の地震対策として今後見直しの予定があるか。
(佐藤知事)
これまで取り組んできた対策を継続しつつ、さらに強化していく方針です。特に、避難所運営に関しては、能登半島地震の状況を踏まえ、孤立集落が発生した際の対応が課題として残っています。今後は、こうした課題にしっかりと対応していく必要があります。
また、ハード面の整備に加えて、ソフト対策の重要性がより増していると考えられます。昨年1年間の状況を見ても、早めの避難をすることよって、関連死を含む死者ゼロという結果につながりました。これは、避難意識の向上による効果が大きいと考えられます。
今後は、大雨や洪水に加え、南海トラフ地震のような大規模災害への備えが重要になります。特に、被害想定上、津波の影響が最も大きいと考えられるため、避難訓練の実施や避難情報への注意喚起をさらに強化し、防災対策を進めていく方針です。
(記者)
先日は、南海トラフ地震臨時情報調査中が出まして、結果的には調査終了になりました。県の方では、臨時情報の調査中や巨大地震警戒・注意といった対応を分けられていると思うが、その点を見直す予定や必要性はあるか。
(佐藤知事)
一応フレームがありますので、そのフレームにしたがって対応していくということでよいのではないかと考えています。
土葬について
(記者)
土葬の関連で宮城県知事が土葬墓地に関して設置の検討を表明するような発言があったが、佐藤知事のお考えは。
(佐藤知事)
地域的な課題として土葬の話が出ていますが、それ以外のところで、今まで私も検討したことはないので、宮城県知事が言われているのがどういうことなのか聞いて、確認していきたいと思います。
(記者)
日出町の宗教法人別府ムスリム教会の土葬墓地を整備する計画の議論に関して、佐藤知事が感じていることはあるか。
(佐藤知事)
基本的に、埋設墓地の業務は、市町村の専管事項になっていますので、注意深く見守っておりますけども、前回の日出町長選挙で争点になった上で、新しい町長が選ばれた経緯もありますので、今の段階ではやはり町の取組を見守るということが適切ではないかなと思います。
鳥インフルエンザについて
(記者)
鳥インフルエンザが、全国的に猛威をふるっているが、今現在の対策はどのように考えているか。
(佐藤知事)
現在警戒を強めておりまして、県内の養鶏業者に対して消毒薬の配布を行い、併せて注意喚起を実施しています。
発生時に最も重要なのは、感染の拡大を防ぐことです。そのため、発生が確認された際には速やかに連絡するよう徹底を図っています。また、発生しないことが何よりですが、万が一発生した場合には、対応方針に基づき、殺処分や搬入・搬出の禁止など、迅速な対応を取ることが不可欠です。この対応は農林水産部が所掌しており、日々警戒を強めながら対応を進めている状況です。
ランピースキン病について
(記者)
ランピースキン病が福岡県で国内初ということで確認されたが、県内の影響や対応策、そのものの重要度などの認識は。
(佐藤知事)
この病気は牛と水牛に影響を与えます。死亡率は低いものの、個体の活力低下や乳牛の乳量減少、流産、不妊、皮膚損傷などが発生します。人への感染はないとのことです。
昨年11月6日に福岡県の乳用牛飼育場で初めて発生し、令和7年1月時点で福岡と熊本でも発生が確認されています。
大分県では、これを受けて生産団体に情報提供と注意喚起文を発出しました。異常が見られた場合には早期通報を促し、蚊やハエが血を吸って他の牛に感染を広げるため、これらの防除を強調しています。また、他の農場で使用した器具などから感染が広がることがあるため、共有する際は器具をしっかりと洗浄・消毒するよう通知文を出しています。
万が一発生した場合は、家畜保健衛生所が立ち入り、農場内で隔離措置を取ることになります。現在のところ、県内の農場で異常は確認されていませんが、引き続き伝染病として適切に対応していくことが求められます。
ホーバークラフトについて
(記者)
ホーバークラフトの進捗状況について、どのような状況か。
(佐藤知事)
今のところ周遊が行われておりまして、年末年始はかなり多くの方に乗っていただきました。一番多い日が4便で318名、強風時に欠航していますが、28日からあとは土日と休みの日ということで1月3日と、この間の1月13日も就航していますが、1月13日は118名と多くの方に乗っていただいています。1月18日、19日の土日から1日2便になっていまして、19日は91名の方に乗っていただいております。定期便の方は、引き続き準備を大分第一ホーバードライブでやっていると思いますので、準備ができ次第、運輸局の検査を受けるということであります。
(記者)
大きな進捗はまだないということか。
(佐藤知事)
そうですね。聞いているところでは大きな進捗はありません。
任期折り返しについて
(記者)
4月で1期目任期の折り返しが見えてくるが、何か意識されていることなどあるか。
(佐藤知事)
あと3か月で任期の半分が経過することになります。昨年は、長期総合計画「安心・元気・未来創造ビジョン2024」を策定し、年末年始には県内各地でその説明会も実施しました。
現在、そのビジョンに基づく部門計画も着々と進んでおり、このような進展は順調に進んでいると言えるかもしれません。
また、新たな取組として、4月には遠隔教育が始まる予定ですし、来年度には大阪・関西万博や宇佐神宮御鎮座1300年の記念式典も控えています。これらに向けて、魅力的な情報発信をさらに進める準備を整えており、これからもその方向で一歩一歩進めていきたいと考えています。
(記者)
「安心・元気・未来創造」の県民への定着はどうか。
(佐藤知事)
説明会を開くと、「こういうふうな形で進めているんですね」というふうにおっしゃってるということは、逆に言うとやっぱり発信しないとなかなか関心持ってもらえないということは確かだと思います。引き続き、情報発信の面で努力をし、また、多方面で話すと個別の意見もいただきますので、実際のニーズに沿った形で進めていくことが何より大事だと思います。発信と意見をいただいてそれを実施に移していくことをきちんとやっていきたいと思います。




