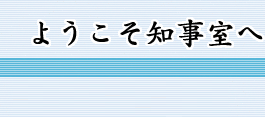
令和7年1月6日知事定例会見
動画はYouTube「おんせん県おおいた公式」へ
日時:令和7年1月6日(月曜日)14時00分~
場所:第一応接室
記者会見時に配布した資料を掲載します。

年頭に当たって
配 布 資 料:なし
明けましておめでとうございます。
項目の前に、年頭にあたってということでお話させていただければと思います。
まず、昨年の振り返りです。
昨年は、能登半島地震や羽田空港での事故があったほか、台風第10号の被害や南海トラフ地震臨時情報の発令などもあり、災害が大変多い年でありました。
海外では、ウクライナ情勢、中東、韓国など様々なところで心配な状況が続いているのではないかと思います。
今年になっても、韓国でのチェジュ航空の事故でありますとか、茨城県沖での漁船の事故など、安全はやはり最重要な課題だということを改めて認識しているところです。
県内では、明るい話題としては、4月から6月のデスティネーションキャンペーンを福岡県、JR九州と一緒に行い、にぎわいを取り戻す非常によいきっかけになったと思います。
11月の全国豊かな海づくり大会では、天皇皇后両陛下をお迎えしました。大分の海の幸、森林や川、海などの自然の大切さを全国に発信するよい機会になったのではないかと考えています。
先日1月1日には、毎年行われます皇居での新年祝賀の儀に県民を代表して参列をさせていただきまして、両陛下とも変わらずお健やかに新年をお迎えされたご様子でございました。
災害の被害も大きかったですが、県内では人命が失われるようなことはなかったということもあり、明るい話題も多い1年だったかなと考えています。
このような中で、県政については、昨年の9月に新たな長期総合計画「安心・元気・未来創造ビジョン2024~新しいおおいたの共創~」を策定し、併せて行財政改革推進計画も策定しています。
昨年の状況を踏まえ、今年は、ビジョンの中でも最初に書いている災害対策に引き続き力を入れていきます。
昨年の補正予算の時にも、能登半島地震の経験を踏まえて、地域防災計画の見直しや、携帯トイレの備蓄の積み増しなどの対策を行いました。
片方で、おおいた消防指令センターが10月から本格運用しており、円滑に運用が行われているところです。
♯7119も、大分市が先行してスタートしておりますが、来年度のできるだけ早い時期に全県展開していくことにより、救急車の一層の効率的な活用ということと、パンデミック等に備えた取組ということでやっていきたいと思います。
今年は昨年のデスティネーションキャンペーンに相当するような大きなイベントとしまして、大阪・関西万博が4月から始まります。
また、宇佐神宮の御鎮座1300年の年であり、1月から県立歴史博物館で、特別企画展を行います。
万博に世界中から様々な方が来られますので、その方々を、大分まで誘客する取組と、大分の様々な魅力を世界に発信していく取組を合わせてやっていきたいと思います。
世界に2か所しかない乗り物であるホーバークラフトも魅力の1つになると思いますので、これもぜひ多くの方々に、期待をしていただければと思います。
年末年始の5日間の周遊では、768名の方に乗船していただきました。
空港側でもイベントを2日間行い、128名の方に参加をいただきました。
やはりホーバークラフトに関心を持って、乗ってみたいという方がたくさんいるなということを改めて実感したところです。
これからまた定期就航に向けても様々な取組が行われますし、大分第一ホーバードライブの方でも観光利用など様々な取組を考えていると思います。そういうものは後押ししていくことも必要かなと思います。
教育では、普通科高校における遠隔教育が今年の4月からスタートします。
まずは、臼杵高校、佐伯鶴城高校、日田高校、宇佐高校からの4校で、数学と英語、2科目から始めます。
レベルとしては通常よりもかなり難易度の高い授業のレベルになります。
そういう授業を受けたいという生徒さんのニーズに応え、どこの高校に進学しても多様で質の高い教育を受けられ、進路を確保できるような体制を整えていくための1年目となります。
広域交通ネットワークでは、東九州新幹線や豊予海峡ルートの実現に向け、引き続き果敢にチャレンジをしていきます。
また、物価と賃金の好循環の実現に向け、昨年もずっとやっておりますが、価格転嫁の推進や政労使での協議などをさらに進めていく必要があります。
物価が上がってきている中で、賃金も徐々に上がってきて、賃金の上昇が、物価を上回る兆しも出てきているかなと思いますので、さらなる賃上げを中小企業ができる環境を整える施策の展開を合わせてやっていきたいと思います。
このような取組をしながら、誰もが安心して元気で活躍できる大分県、知恵と努力が報われ未来を創造できる大分県を目指していきます。
午前中の仕事始め式では、特に若い職員が安心して仕事ができる職場環境づくり、若い職員が育っていく職場づくり、女性の職員も同じでありますが、そういう皆さんが活躍できる風通しがよい職場環境を特に幹部の皆さんにしっかりつくっていくようにと話をしました。
今年の巳年は乙巳(きのとみ)ということですが、努力を重ねて物事を安定させていくという意味合いがあるということですので、努力を重ねながら、様々な計画を実現に移していく年にしたいと考えています。
安心・元気・未来創造ビジョン2024
配 布 資 料:安心・元気・未来創造ビジョン2024 [PDFファイル/2.66MB]
お手元にお配りしているとおり、安心・元気・未来創造ビジョン2024の冊子ができました。
昨年9月に議会で議決いただき、これから10年、毎年フォローアップしながら運用していくことになります。
県の最上位の長期総合計画としまして、これに環境や教育、福祉の計画など、様々な部門計画が実施計画としてぶら下がっていて、実行していくことになります。
各地域で講演会も行っており、昨年12月には、佐伯と大分と日田で行いました。今月には、国東と宇佐と、竹田でも行う予定です。
その他に、年末に高校生との意見交換を行い、将来に対してどういう夢を持っているかというような話を聞きました。
非常に面白く、ずっと大分で活躍したい、大分県に貢献したいという声もあれば、いろいろな可能性を試したいという声もありました。
県民の皆さんに少しでも読んでいただき、意見をいただいて、それを政策に反映させていきたいと思います。
冊子の内容はホームページにも、掲載しています。
ぜひご覧になってください。
記者質問
フリーアドレス化について
(記者)
仕事始め式の際にもあいさつがあったように、風通しのよい職場づくりに向けて、行政企画課がフリーアドレスを導入しているが、全庁的に進めていく方針はあるか。
(佐藤知事)
具体的に例を挙げてお話しするようなものはまだないですが、何かありますか。
(総務部長)
即座にフリーアドレスということではないですが、行政企画課でやってきたことを横展開ができるようなことも考えていきたいです。
ホーバークラフトについて
(記者)
大分第一ホーバードライブの社長が昨年末に、令和6年内の定期就航はないということを、記者会見で話したが、知事として、定期就航をいつごろに始めてもらいたいという意向を持っているのか。
(佐藤知事)
もちろん早い方がいいですが、安全第一であり、定期航路の方はまだ運輸局による安全確認検査が終わっていません。
安全確認検査が終わって、就航ということでありますので、あくまでも安全第一として準備をしてもらいたいと思います。
(記者)
知事の中ではいつぐらいまでに安全確認検査を終わらせて、定期就航してほしいと思っているのか。
(佐藤知事)
例えば、4月からは万博も始まりますので、大分の魅力の1つにホーバークラフトに乗れるということが加われば、さらなる誘客につながるという期待はあります。
ただ、あくまでも安全第一でありますし、定期就航の安全確認検査に向けて、様々な議論を大分第一ホーバードライブがしていると聞いていますので、そういうところも含めて、大分第一ホーバードライブの判断で、安全確認検査が受けられると判断をすれば、可及的速やかに検査を受けて、定期就航に入っていくことになるだろうと思います。
(記者)
少なくとも、年度内には定期就航を始めてもらいたいか。
(佐藤知事)
いつごろやってもらいたいというのはなく、安全の確認ができれば、可及的速やかに就航してもらいたいと思っています。
4月からと言っているわけではありません。
人件費などすべての経費は大分第一ホーバードライブに全部かかっていますので、大分第一ホーバードライブはできるだけ早く運航したいというのは当然のことだと思います。
遠隔教育について
(記者)
遠隔教育導入の学校と教科はどのような判断から選択されたのか。
(佐藤知事)
この遠隔教育はどちらかというとかなりハイレベルの授業を配信しようというものです。
そのため、教科は、レベルが非常にばらつくもので、まずは英語と数学から始めることになりました。
各校の校長先生と教育委員会の担当者が頻繁に意見交換をしながら、どのようなニーズが高いかということなどを議論しながら決めています。
学校は、準備ができたところから順番にやっていくということであります。
受け手の側の機器の準備もありますし、ニーズがどのぐらい高いかなど、決める際の詳細については担当課へ取材をお願いします。
(記者)
県議会などでは、全県1区の見直しと合わせて議論されることがあったかと思うが、その関連では、この遠隔教育というのはどのような位置づけとなるか。
(佐藤知事)
遠隔教育は全県1区の見直しの有無に関わらず進めていくということであります。
全県1区の見直しの方は、今委員会を作って検討されています。
これは粛々と、検討していきますが、その時に遠隔教育でどの程度カバーできるかというところも併せて議論されることになると思います。
健康寿命について
(記者)
昨年末発表があった健康寿命について、順位を大きく落としているが、大きく落ちた要因と、今後どこに力を入れていくのか。
(佐藤知事)
令和元年の調査では男性が1位で女性が4位でした。令和4年の調査では、男性が25位で女性が10位ということです。
特に男性はかなり大きく落ちました。
令和元年の調査時は、高齢者の方の通いの場への参加率が高かったことが効いていたのかなと考えられています。
コロナ禍になり、この通いの場への参加率が低くなっていたので、その影響も出てきているのではないかと考えています。
今また、通いの場が徐々に復活してきており、こういう出かけるところがあって体操したり、他の人と話をしたりするというのが、健康寿命を延ばすのに非常に大きな効果があると考えています。
こういう通いの場をさらに拡大をしていって、県民総ぐるみの健康づくり運動にしていこうと考えています。
そして、健康アプリも本格稼働をこの4月からする予定にしていますので、そういうものも活用して、また健康寿命日本一を目指していきたいと思っています。
人口減少対策について
(記者)
人口減少対策について知事のお考えを。
(佐藤知事)
人口減少対策は自然増対策と社会増対策の2通りあります。
1つ目の自然増対策では、高齢者の方は元気に長生きしていただくこと、同時に生まれてくるお子さんを増やしていくということです。
本県では毎年1万人程度、自然減となっています。
生まれてくるお子さんが減っているので、例えば出会いの場などの婚活イベントをはじめ、子育て支援を充実させていくなど、様々な形でサポートしていくということになるだろうと思います。
結婚した方のお子さんの数は大体2人ぐらいで昔からあまり変わってないらしいので、やはり結婚しない方が増えているというのが少子化の大きな要因になっているようです。
そこのところは突き詰めて考えると、1つは収入がずっと上がってこなかったことによって、結婚の希望があるけれど、なかなか結婚しない、お子さんを持たないという方々がいるということのようです。
ここは賃上げ対策や収入が上がっていくような対策が大事だと思います。
また、結婚や子育ては、たくさんの喜びがあるというメッセージを出していくのも大事かなと思います。
2つ目の社会増対策では、移住者は徐々に増えてきていますが、住んでみたい、訪れてみたいという方々に実際に来てもらうために、魅力をどう高めていくかが大切です。
また、例えば高校生や大学生の就職の時に、地元の中小企業とのマッチングや、県外に出ても、戻って来られるように取組を行っていくなども大事です。
住宅政策ですと、近居同居のような形で親の近くで住むときに支援する施策も県、市町村で行っています。
さらに充実させるために、空き家のマッチングを進めていくとか、空き家の活用を進めていくとか、住宅が非常に重要だという話も専門家からよく聞きます。
県営住宅では、今は3DKの間取りが多いですが、その間取りだとお子さん1人で窮屈になります。
そのため、お子さんが多い世帯でも利用しやすいような間取りにするとか、県営住宅を建て替える際には、不自由なく子育てできるような間取りや大きさにするとか、そういうことも併せて行っていく予定にしています。
これが決め手ですというのはなかなかないと思いますので、いろいろなことをやっていかないといけないと思います。
賃上げ対策について
(記者)
行政が賃上げにどのように絡んでいくのか。
(佐藤知事)
いろんな手だてはありますが、中小企業においては賃上げをしたいが、原資がないという場合があります。
そのための対策として、1つは価格転嫁を円滑に進められるように、大企業に対して働きかけをさらに進めていくということがあります。
政労使が集まった会議の場で、大企業も含めて中小企業の賃上げの確保ができるような環境づくりをしていくことが大事であるという確認をするなどもあります。
それから、企業が省力化で生産性を上げていくときに補助金が出るような施策がありますが、賃上げをした企業に対してはその補助率、補助額を引き上げ、その原資を使って賃上げしやすいような、省力投資の後押しをしていくことを昨年からやっています。
また、融資についても、生産性を上げ、賃上げを予定しているところについては優遇措置をすることをやっております。
新しいものを導入するときの実証支援を県として行うことも必要になってくるかなと思います。
空飛ぶクルマについて
(記者)
空飛ぶクルマの社会実験的なものを大分県で行う考えはあるか。
(佐藤知事)
空飛ぶクルマは、今、法政大学のベンチャー企業に県央飛行場をフィールドとして提供しています。
まだ発表されてないかもしれませんが、(民間企業が)空飛ぶクルマを飛行させる実証実験を本年度中にやる予定にしています。
実証支援をすることも自治体の大事な役割だと思います。
週休3日について
(記者)
働き方改革関連で週休3日制を大分県で導入する考えはあるか。
(佐藤知事)
まだそこは議論したことがないので、今のところ予定はありません。
インフルエンザ感染動向について
(記者)
インフルエンザの感染が年末にかけてすごく高まっていて、この年末年始を経て何か特筆すべき変動や呼びかけ等はあるか。
(佐藤知事)
インフルエンザが非常に流行しているということで、年末に薬や熱冷ましなどを事前に準備して、気をつけてくださいというお願いをしました。
(福祉保健部審議監)
年末に発表した感染動向が51週の分で、52週の分が今週の水曜日に集計がまとまりますので、年末の動向はまだ明らかになってないという状況です。
防災対策について
(記者)
安心・元気・未来創造ビジョン2024の個別の項目中で人的被害ゼロという打ち出しをしているが、改めて人的被害ゼロに向けた決意を。
(佐藤知事)
防災対策において、人的被害ゼロが最も大事だと思っています。
人命が失われてしまうと回復できませんので、そういう意味では人命被害ゼロを目指して取り組んでいきます。
災害時の被害もそうですし、2次的な健康被害で亡くなる方も含めて、どういう対策をしていくのかが一番重要だと思っています。
昨年も、ちょっと間違えば人命を失ったというケースもありましたが、早めの避難をしてもらうことにより、結果として、被害がゼロだったということもありました。
これからも、早めの避難、備え、それから情報の提供も含めて、空振りになってもいいので、危ないと感じたら避難をするということをぜひ県民の皆様に訴えていきたいです。
そのためにも、防災意識を持ってもらうことが大事ですから、避難訓練や消防の出初め式など1つひとつ積み重ねをしていきたいです。
2次的な健康被害という意味では、避難所運営というところで、能登半島地震の経験から学ぶべきところがたくさんありますので、そういうものも充実していかないといけないと思います。
カスハラ対策について
(記者)
人事課から発表された県のカスハラ対策のマニュアルについて、職員アンケートで5年以内に1,000人以上の職員が何らかの被害を受けたという結果が出ているが、知事としてはどう感じるか。
(佐藤知事)
やはり毅然とした対応を組織として行うことが非常に大事であり、現場が少し我慢すればいいとか、現場でうまく対応すればいいということではなく、職員が安心して働ける環境を整える意味でも、こういうのは管理職と現場の人たちが一体となって取り組んでいかないと、実が上がってきません。
そういう意味でマニュアル化をして、何かあったときには、管理職の人たちが前に出て対応していくということが確認できたのではないかと思います。
言いたいことをしっかり言っていただいて、行政に生かしていくことは大事だと思っています。
ただ、それにより、例えばコロナ禍の時に、健康相談したいのに電話がふさがってしまってつながらないとかいうことがありましたが、そういうことも起こってしまいます。
バランスを考えていただいて、ほかの方のことも考えていただいて、対応していただくようにお願いしたいと思います。
(記者)
直接被害を受けた職員が1,100人と、回答者の46.8%で半数近くと多いイメージを持ったが、結果について、どういう印象を持っているか。
(佐藤知事)
ハラスメントの受けとめ方はいろいろありますが、必要以上の長時間の対応をしたり、大声で言われたりとか、不当な要求をされた経験をした人は多分これぐらいいるだろうなと思います。
戦後80年について
(記者)
今年は戦後80年を迎えるということで、県として取り組んでいきたいこと、発信していきたいことがあれば。
(佐藤知事)
戦後80年間、戦争しない国として続いてきているのは、やはり大変立派なことだなと思いますし、それを今後も続けていくことは大変重要だと思います。
そのために平和や人権の大切さを引き続き発信をしていくことが大切なのではないかと思います。
(記者)
具体的にやっていこうといえるようなものは。
(佐藤知事)
今のところ予定してないです。
例えば憲法セミナーや人権セミナーなどのイベントの機会をとらえて、何かやっていくべきじゃないかなと思います。




